長年連れ添った夫から突然「離婚したい」と言われたら、戸惑いと衝撃は計り知れないでしょう。とくに50代ともなると、子育てが一段落し、これから夫婦二人で穏やかな老後を迎えるはずだったと考えていた方も多いはずです。実際、近年では夫から離婚を切り出す熟年離婚が増加傾向にあり、長年連れ添った妻が突然「離婚したい」と言われるケースも少なくありません。
しかし、感情に流されるのではなく、冷静に現状を把握し、適切な対応を講じることが重要です。本記事では、50代で夫から離婚を切り出された場合に知っておくべき留意点について、行政書士の立場から丁寧に解説いたします。
50代で離婚したいと夫から言われる理由とは
![]()
まず、50代で夫から離婚したいと言われるのは、一体どのような理由が背景にあるのでしょうか。熟年離婚に踏み切る夫の本音を理解することで、今後の対応策が見えてくるかもしれません。以下では、夫が50代で離婚を切り出す主な理由を3つご紹介します。
長年の不満の蓄積と心のすれ違い
結婚生活が長くなる中で、夫婦間の価値観の相違やコミュニケーション不足が積み重なり、夫が不満を抱えてしまうケースがあります。
例えば、「妻から思いやりや感謝の気持ちが感じられない」「自分に関心を持ってくれない」といった訴えは、熟年離婚を決意する夫によく見られる本音です。
こうした不満が長年蓄積すると、「今まで家族のために頑張ってきたが、もう義務は十分果たした」と考え、子育てや住宅ローン返済が一区切りついたタイミングで離婚に踏み切る夫もいます。
つまり、長年のすれ違いから夫婦関係に虚しさを感じ、50代になってから離婚を切り出す場合があるのです。
子どもの自立・定年に伴う決断
50代という年齢は、多くの家庭で子どもの自立や夫の定年退職といったライフステージの大きな変化が訪れる時期です。子どもが独立し夫婦二人だけの生活になると、それまで見えてこなかった夫婦間の問題が表面化することがあります。
また、定年を控え「このまま残りの人生をこのパートナーと過ごしてよいのか」と夫が真剣に考え始める時期でもあります。その結果、「残りの人生は自由になりたい」「一人になって好きなことをしたい」といった理由で、夫が離婚を申し出るケースも見られます。子どもの成長や定年という節目が、夫に熟年離婚の決断を促すことがあるのです。
他の女性の存在や新たな人生の模索
夫から50代で離婚を切り出された背景には、夫の不倫や新しいパートナーの存在が潜んでいることもあります。長年の結婚生活で妻に対して失望感を抱いた夫が、「長く付き合っている不倫相手と一緒になるため」に離婚を決意するケースも少なくありません。
妻との関係で愛情や尊敬が薄れたところに別の女性の存在があれば、夫にとって「今の妻と別れて新しい幸せを掴むチャンス」と映ることがあります。このように、他の女性との再スタートを目指して熟年離婚に踏み切る夫もいるのです。
【関連記事】
熟年離婚でスッキリ解決!
熟年離婚の原因に多いモラハラとは?
熟年離婚の準備で女性がするべきこと
50代で離婚したいと夫から言われたら応じるべき?
![]()
突然夫から離婚を求められたとき、すぐにその要求に応じるべきかどうか、悩む方は多いでしょう。離婚に応じるか否かの判断は非常に重要で、自分の今後の人生に大きく影響します。この章では、夫からの離婚要求に対して応じるべきか迷ったときに考慮すべきポイントを解説します。
簡単に応じず冷静な判断を
まず大切なのは、安易に離婚に同意しないことです。突然の離婚話に動揺し、「早くこの状況から解放されたい」と焦る気持ちから即座に離婚届に判を押してしまうのは避けましょう。50代での離婚は、経済的にも精神的にも大きな変化を伴います。
一時的な感情で決断すると、後々「こんなはずではなかった」と後悔する可能性があります。夫から「離婚したい」と言われても、まずは深呼吸して冷静になり、自分にとって最善の選択は何かをじっくり考える時間を持つことが重要です。
離婚に応じた場合のメリット・デメリット
次に、夫の要求に応じて離婚する場合のメリットとデメリットを整理しましょう。メリットとして考えられるのは、夫婦間の葛藤やストレスから解放され、自分らしい第二の人生を歩める可能性があることです。もし結婚生活が長年つらいものであったなら、離婚によって心機一転、新たなスタートを切れるかもしれません。
一方、デメリットとしては、経済面での不安や社会的な変化が挙げられます。とくに専業主婦であった場合、離婚後の生活費をどう確保するかは大きな課題です。また、長年連れ添った配偶者と別れる精神的な喪失感や、親族・友人間での戸惑いも生じるでしょう。夫からの離婚の提案に応じるかどうかは、こうした利点と欠点を天秤にかけ、自分にとってどちらがより受け入れられるかを考える必要があります。
離婚の決断に悩むときは専門家へ相談
離婚するべきか迷ったときは、第三者の専門家に相談することも有効です。一人で悩んでいると視野が狭くなりがちですが、カウンセラーなどに話を聞いてもらうことで、客観的なアドバイスを得られます。
また、すぐに結論を出せない場合には別居という選択肢もあります。一定期間離れて生活することでお互いの大切さに気付き、関係が修復する夫婦もいれば、逆に離婚への気持ちが固まる場合もあります。いずれにせよ、専門家に相談しながら冷静に検討することで、後悔の少ない決断につなげることが大切です。
【関連記事】
離婚したいけどできない女性の特徴とは?
離婚したいけど何から始めていいかわからない方
50代で離婚したいと夫から言われた/離婚に応じるケース
![]()
夫からの離婚要求に応じると決めた場合、円満に離婚を進めるために押さえておきたいポイントがあります。ここでは、話し合いの進め方から合意内容の書面化、そして離婚協議書や公正証書といった正式な書類の作成まで、離婚手続きを進める上で重要なステップを解説します。
まずは夫婦で十分に話し合い
離婚に応じると決めても、すぐに役所へ離婚届を提出するのではなく、まずは夫婦でしっかりと離婚条件の話し合いを行いましょう。財産分与や年金分割、慰謝料の有無など、離婚に伴う取り決め事項を一つ一つ確認していく必要があります。
たとえば、共有財産である自宅や預貯金をどのように分配するか、夫が退職金を控えている場合その扱いをどうするか、結婚期間中に築いた年金を分割する手続きはどうするか、といった点です。また、50代での離婚の場合子どもは成人しているケースが多いですが、もし未成年の子どもがいるなら、親権者や養育費、面会交流の取り決めも必要になります。
離婚の合意自体は比較的容易でも、細かな条件面で揉めないよう、双方の希望を出し合って納得いくまで話し合うことが重要です。
話し合いの内容を書面に残す
口頭でどんなに約束しても、後から「言った/言わない」のトラブルになってしまっては元も子もありません。そこで、話し合いで合意した内容は書面に残すようにしましょう。
自分たちでメモ書き程度でも構いませんが、できれば正式な合意書として体裁を整えることをおすすめします。それが「離婚協議書」と呼ばれる書面です。離婚協議書は、夫婦が合意した離婚条件をまとめた文書で、後日の紛争防止に大いに役立ちます。
合意内容を書面化することで、双方が内容を再確認できますし、署名押印をしておけば法的な証拠にもなります。特に金銭の支払い(財産分与の支払い方法や慰謝料の分割払いなど)が伴う場合、書面がなければ約束を反故にされるリスクが高まります。必ず合意事項は文書化し、夫婦双方で内容を確認しましょう。
離婚協議書と公正証書とは?記載すべき内容
離婚協議書とは、先述の通り夫婦間の離婚の合意内容を書面にまとめたものです。これに対し、公正証書とは公証役場で公証人が作成する公的な文書で、離婚協議書をより強力な形にしたものといえます。
公正証書にしておく最大のメリットは、養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合に、裁判をしなくても強制執行(差し押さえ等)が可能になる点です。では、離婚協議書(公正証書)には具体的にどのような内容を記載すべきでしょうか。一般的には以下の項目を盛り込みます。
- 離婚の合意:夫婦が協議離婚に合意した旨
- 財産分与:現金・預貯金、不動産(自宅など)、車、保険、退職金などの財産分与の方法
- 年金分割:厚生年金など婚姻期間中の年金記録の分割取り決め(実施方法や割合)
- 慰謝料:夫に不貞行為など離婚原因の責任がある場合の慰謝料の額と支払方法
- 養育費・親権:未成年の子がいる場合、親権者の指定と養育費の額・支払期間・方法、面会交流の取り決め
- 清算条項:上記以外に一切の金銭請求をしないことを互いに確認する条項
これらの項目を網羅して離婚協議書を作成し、可能であれば公正証書化しておくことで、離婚後のトラブルを防止できます。書類の作成にあたっては法律用語も多く難しいため、行政書士など離婚協議書の作成を専門とするプロに依頼するのも良いでしょう。
行政書士は離婚協議書の作成代行や、公証役場での公正証書作成手続きについてサポートすることができます。適切な書式で重要事項を漏れなく盛り込んだ書面を用意しておけば、50代からの新たな人生を安心してスタートさせることができるはずです。
50代で離婚したいと夫から言われた/離婚に応じないケース
一方で、夫から「離婚したい」と言われても離婚に応じない選択をするケースもあります。妻側に離婚の意思がない場合、すぐに離婚が成立することはありません。この章では、離婚に応じたくないときに取るべき対応や、法的な流れ、そして今後に向けて準備すべきことについて説明します。
離婚に応じない意思を伝え関係修復を模索
夫から離婚を切り出されたものの、「どうしても離婚したくない」という場合は、まず自分の意思をはっきり伝えることが大切です。曖昧な態度で先延ばしにするのではなく、「離婚には同意できない」という意思を夫にしっかりと示しましょう。
その上で、可能であれば夫婦関係の修復を試みます。夫が離婚を考えた理由について冷静に話し合い、お互いに歩み寄れる点がないか探ってみてください。場合によっては、夫婦問題に詳しいカウンセラーや第三者を交えて対話するのも有効です。
長年連れ添った相手との関係ですから、感情的なしこりは簡単には解消できないかもしれません。しかし、50代という人生の節目において、今一度夫婦の絆を見つめ直す努力をする価値はあるでしょう。「まだやり直せる」「修復できるはずだ」という希望が少しでもあるなら、すぐに離婚届を書く必要はありません。
離婚を拒否する場合の法的な流れ
妻が離婚に応じない限り、夫婦は協議離婚(話し合いによる離婚)を成立させることはできません。夫が一方的に離婚届を提出しても、妻の署名捺印がなければ役所は受理せず無効になります。
夫がそれでも離婚を望むなら、次のステップは家庭裁判所での調停です。調停委員を交えた話し合いでも妻が離婚を拒否すれば、最終的には離婚裁判(訴訟)に進む可能性があります。
裁判になった場合でも、直ちに離婚が見込まれるわけではありません。法律上の離婚原因(不貞行為や悪意の遺棄、長期の別居など)が必要で、夫にこれといった離婚事由がない場合、裁判所が離婚を認めないこともあります。
特に夫側に有責(例:夫の不倫)があるケースでは、たとえ夫が離婚を望んでも簡単には認められない傾向があります。ただし、実際には別居が長期化すれば婚姻関係の破綻が認められてしまう可能性もあります。いずれにせよ、離婚に応じない意思を貫く場合は、このような法的プロセスを経ることになる点を念頭に置きましょう。
離婚に応じない場合に備えるべきこと
離婚を拒否して夫婦関係を継続する場合でも、将来に備えた準備はしておくべきです。まず、夫が家を出て別居に至った際には、婚姻費用の分担を請求することを検討しましょう。婚姻費用とは、夫婦が別々に生活する間の生活費の分担金のことで、収入の多い夫から妻へ生活費を支払ってもらう制度です。
別居に移行したとしても、離婚が成立しない限り夫には婚姻費用の支払い義務があります。家庭裁判所に申し立てを行えば、適切な金額を算定してもらえるので、生活に不安がある場合は遠慮せず利用しましょう。
また、今後万一裁判になった際に備えて、証拠や資料の整理も大切です。例えば、夫に不倫相手がいるならその証拠、夫婦の共有財産や年金額の資料などの情報を整理しておきます。
加えて、自身の今後の生活設計も現実的に考えてみてください。万が一数年後に離婚が避けられなくなった場合でも困らないように、収入源の確保や実家・友人の協力体制など、セーフティネットを意識して準備を進めておくことは重要です。
最後に、離婚問題が長期化すると精神的にも疲弊します。不安なときは一人で抱え込まず、信頼できる友人や専門家(行政書士等)に相談しながら、自分の人生を守る行動を取っていきましょう。
離婚協議書や公正証書の作成は当事務所にご相談ください
![]()
50代という人生の転機において離婚を選択することは、大きな決断です。そしてその後の生活を安定させるためにも、財産分与や年金分割、慰謝料、婚姻費用、親権などをしっかりと取り決めた上で、「離婚協議書」や「公正証書」として残しておくことが非常に重要です。
特に、次のようなお悩みをお持ちの方は、文書による取り決めを強くおすすめします。
- 夫婦共有の預金や不動産の分け方でもめたくない
- 夫が退職金を受け取ったあとに財産分与を確実に受け取りたい
- 年金分割を確実に実施したいが手続き方法が分からない
- 慰謝料や婚姻費用の支払いが本当に守られるか不安
- 別居後や離婚後の生活費が確保できるか心配
- 「言った/言わない」の争いを避けたい
当事務所では、熟年離婚に特化した離婚協議書や離婚給付契約公正証書の作成支援を行っております。行政書士として、内容の整理から文案の作成、公証役場とのやり取りまで一貫してサポートいたします。「どんな内容を盛り込むべきか分からない」「離婚後の生活が不安」という方も、安心してご相談ください。一人で悩まず、専門家に頼ることが、後悔しない離婚への第一歩です。
まずはお電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。あなたのこれからの人生を、法的書面でしっかりと支えるお手伝いをいたします。
サービスの特徴
- きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。 - 柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。 - 明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。 - 全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。
離婚協議書作成の流れ
- 初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。 - 契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。 - 協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。 - 協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。 - 協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| ⑴離婚協議書の作成と製本 | 44,000円 | 離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。 |
| ⑵離婚公正証書の作成サポート (上記⑴を含みます。) | 77,000円~ | 離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。 |
※)上記金額に実費がかかります。
当事務所にお任せいただくメリット
- 安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。 - 時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。 - トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。 - 専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。
お問い合わせ
離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
お客様の声
お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。
![]()
【政府の記事】
日本年金機構「離婚時の年金分割」
法務省「年金分割」
法務省「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」
厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」

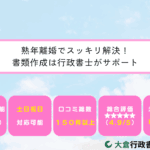

コメント