40代で専業主婦として長年家庭を支えてきた方が離婚を考えるとき、まず心配になるのは離婚後の仕事ではないでしょうか。ブランクの長さや年齢を考えると、再び社会に出て働くことに不安を感じる方も多いでしょう。実際、40代での再就職は決して簡単ではないのが現状です。しかし、準備次第で40代からでも新たな一歩を踏み出すことは十分可能です。
本記事では、40代女性の離婚後の仕事選びで直面する課題とその対策について行政書士の視点から解説します。40代で離婚後に再就職する難しさと乗り越え方、扶養を外れる際の社会保険手続きと負担、40代での副業・フリーランスという働き方、そして離婚協議書・公正証書による生活安定策までを取り上げます。離婚後の「仕事」と「生活」に向けて不安を解消し、前向きなスタートを切るための参考になれば幸いです。
40代で離婚後に再就職する難しさ
働くことへの不安とブランク・年齢の壁
![]()
長年専業主婦として家庭に専念してきた方にとって、久しぶりに外に出て働くことには大きな心理的ハードルがあります。特に40代ともなると、「今さら社会で通用するだろうか」「若い人についていけるか」といった不安を感じるのは自然なことです。さらにシングルマザーとなる場合、家事や育児と新しい仕事との両立ができるかという心配もあります。
実際問題として、ブランク(空白期間)の長さや年齢が再就職の場面で壁になる現実も否めません。企業側は長期間職場を離れていた人に対し、「即戦力になるか」「新しい環境に適応できるか」を慎重に見極めようとするため、ブランクが長いだけで書類選考や面接で不利に働いてしまうケースがあります。また、日本の雇用慣習では年齢による制約が根強く、40代という年齢だけで採用のハードルが上がってしまうこともあります。特定の職種で十分な実務経験がない「未経験」の状態であれば、応募できる求人が限られるといった事情もあるでしょう。とはいえ、近年では人手不足の影響もありブランクOK・未経験歓迎とする求人も増えてきています。悲観しすぎず、これまでの人生経験で培った強みをアピールする姿勢が大切です。
どんな求人が多いのか?採用されやすい仕事は?
では、離婚後の40代女性には実際どのような求人が多いのでしょうか。まず多いのは以下のようなパートタイムや派遣社員などの求人です。
- 販売・接客業(例:スーパーや飲食店のスタッフ)
- 清掃の仕事(ビル清掃やホテル客室清掃)
- 工場や倉庫内の軽作業スタッフなど
こうした職種はシフトの融通が利くものも多く、子育てとの両立を目指すシングルマザーにとって取り組みやすい傾向があります。事務職志望の場合は、パソコンの基本スキルがあれば派遣会社経由で一般事務・経理補助などの仕事に就ける可能性もあります(「主婦歓迎」の案件も存在します)。正社員求人となると数は減りますが、全く無いわけではありません。特に人材不足が深刻な業界では年齢を問わず募集をかける企業もあります。例えば、介護業界は40代未経験でも採用されやすい分野の一つです。厚生労働省のデータによれば介護職員として働く女性の平均年齢は45.8歳であり、若い世代だけでなく中高年の力が求められています。介護職は働きながら資格を取得できる支援制度もあるため、未経験の40代女性でもチャレンジしやすいでしょう。このほか、販売・営業職は成果が重視される分、年齢より実績や人柄を評価してもらえる可能性があります。清掃員や警備員のように人手不足の現場も狙い目です。
【関連記事】
>熟年離婚の準備で女性がするべきことを行政書士が解説
扶養から外れることの現実と社会保険の負担
離婚と同時に扶養を外れる影響
![]()
離婚に際して押さえておきたいのが、配偶者の扶養から外れることによる生活面への影響です。専業主婦として夫の会社の健康保険に被扶養者として加入していた場合、離婚届を提出した時点でその資格を失い、夫の健康保険証は使えなくなります。
同様に、厚生年金の第3号被保険者(扶養枠)であった人は、離婚後は自分で国民年金に加入し保険料を納める必要があります。これらの手続きを怠ると無保険の期間が生じたり、医療費を全額自己負担する事態になりかねませんので注意しましょう。
国民年金・健康保険の加入手続き
夫の扶養を外れた後は、速やかに国民年金と国民健康保険への加入手続きを行います。具体的には、市区町村役所で国民年金の変更届と加入届を提出します。2025年度現在、国民年金保険料は月額約1万7千円です。収入が少ない場合でも原則としてこの保険料を自身で負担する必要があります(所得状況に応じて免除や減額の制度もあります)。
扶養喪失に伴う生活費増加のリスク
扶養から外れることで発生する社会保険料の自己負担は、離婚後の生活費を大きく押し上げる要因となります。離婚前には夫の給与から控除されていた厚生年金保険料や健康保険料を、自分の収入から支払うことになれば、合計で月に数万円の負担増になることもあります。収入が安定するまでの間、この負担は家計を直撃するでしょう。離婚後の生活設計を立てる際は、「毎月どれくらいの支出増になるか」「そのためにはどれくらい稼ぐ必要があるか」をシミュレーションしておくことが重要です。可能であれば離婚前にある程度の貯蓄を確保しておく、実家の協力を得るなど、生活費増加への備えも検討しておきましょう。
【関連記事】
>40代女性で離婚した後の一人暮らしが不安…
40代での副業・フリーランスという選択肢
在宅ワークやスキルを活かす働き方
![]()
40代で離婚後の生計を立てるには、会社勤め以外の働き方も選択肢に入ります。最近はインターネットを活用した在宅ワークや、特定の技能を活かしたフリーランスの仕事も増えてきました。例えば文章を書くのが得意なら在宅ライター、語学力があるならオンライン講師、ハンドメイドが好きならネット販売、といったように自分の「好き」や「得意」を仕事につなげることもできます。
自宅で完結できる仕事は通勤時間が不要で、育児中でも子どもの傍にいられるという大きなメリットがあります。もっとも、フリーランスや出来高制の在宅ワークは収入が不安定になりがちです。最初は生活費の一部を補う副業として始め、軌道に乗ってきたら本格的に取り組む、といった段階的な進め方が安心でしょう。離婚後すぐに高収入を得るのは難しいかもしれませんが、小さな仕事からでも実績を積み重ねていけば将来的に収入を伸ばすことも可能です。まずはできる範囲で挑戦してみることが大切です。
パートと副業の組み合わせで収入確保
安定した正社員の職にすぐ就けない場合、パートタイムの仕事と在宅副業を組み合わせて収入を確保する方法もあります。例えば、昼間はパート勤務で基本的な生活費を稼ぎ、夜は子どもを寝かしつけた後に在宅でデータ入力の仕事をする、といった働き方です。収入源を複数持つことで、一方の収入が減った際も他方で補えるというメリットがあります。反面、働きすぎによる体力面の負担には注意が必要です。特にシングルマザーの場合、自身の健康を損なっては元も子もありませんので、無理のない範囲で仕事を掛け持ちしましょう。
子育てと仕事を両立しやすい働き方の事例
40代で離婚しシングルマザーとなった場合、子育てと仕事の両立は大きな課題です。しかし、工夫次第で両立を実現している事例も数多くあります。例えば、ある40代の女性は正社員再就職にあたり時短勤務や在宅勤務制度のある企業を選び、子どもの帰宅時間に合わせて勤務時間を調整している方もいれば、別のケースでは、日中は子どもを保育園に預けてパート勤務し、夜に在宅で副業を行うことで育児との両立を図っている方もいます。
離婚協議書や公正証書で生活を安定させる準備
![]()
40代で離婚を選択した専業主婦にとって、離婚後の収入が安定するまでにはどうしても時間がかかります。特に、再就職の目途が立っていない段階では、生活費や子どもの養育費、老後の資金などに関して強い不安を感じるのが現実です。そのため、離婚時には今後の生活設計を見据えたうえで、経済的な取り決めを文書として明確に残しておくことが非常に重要です。
ここでは、離婚後の生活を安定させるために取り決めておくべき主要な項目について整理し、分かりやすく4つのポイントで解説します。
財産分与(預貯金、退職金、扶養的財産分与を含む)
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分ける制度です。名義がどちらであっても、共に築いたものとみなされるため、実際の生活費に大きく影響する重要な取り決めになります。
対象となる財産には、預貯金、不動産、車両、保険の解約返戻金、株式、退職金などが含まれます。特に退職金は将来の支給予定であっても婚姻期間中に積み立てられた分に関しては分与の対象となり得ます。
加えて、扶養的財産分与という考え方もあります。これは、離婚後に収入が不安定な配偶者の生活を一時的に支援する目的で行う金銭の支給を指します。たとえば「離婚後2年間、毎月10万円を生活支援金として支払う」といった取り決めです。これにより、離婚後の自立準備期間を少しでも安心して過ごすことができます。
養育費(子どもの生活費や教育費の確保)
子どもがいる場合には、養育費の取り決めが非常に重要です。養育費とは、未成年の子どもを育てるために必要な生活費・教育費を、親権を持たない側の親が負担するお金のことです。
養育費は、金額、支払方法(毎月末に指定口座へ振込など)、支払期間(通常は20歳または大学卒業まで)、その他支払いの見直し方法など、できるだけ詳細に決めておく必要があります。
たとえば、子どもが成長するにつれて必要な費用が増えることも想定し、「将来の進学時に一時金として加算する」といった柔軟な取り決めも可能です。
慰謝料(不貞行為や精神的苦痛に対する補償)
離婚原因が不貞行為や家庭内暴力などの場合、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求できる可能性があります。金額の相場はケースによって異なりますが、例えば不貞行為の場合、婚姻期間や精神的ダメージ、子どもへの影響などを踏まえて100万円~400万円とされることが一般的です。
年金分割(老後の生活のための保障)
40代の離婚では、将来の老後資金にも注意が必要です。夫が厚生年金や共済年金に加入していた場合、結婚期間中に形成された年金記録の一部を配偶者に分割できる制度が年金分割です。これによって、離婚後に年金を受給する際、妻自身の年金額に反映されるようになります。ただし、年金分割には分割割合の合意と年金事務所への届出が必要です。
この分割割合(最大50%)は、話し合いで取り決めることができます。なお、年金分割の手続きには離婚から2年以内という期限がありますので、注意が必要です。
なお、上記で記載した取り決めは、いずれも口約束では後のトラブルにつながりやすいため、必ず離婚協議書や公正証書などの書面で残すことが基本です。さらに、金銭の支払いや生活設計に関わる内容を含む場合には、強制執行可能な公正証書にしておくことが望まれます。
【関連記事】
>離婚したいけどお金がない40代・50代の悩みを行政書士が解説
>離婚したいけど何から始めていいかわからない方は必見です
公正証書とは?作成するメリット
離婚協議書は当事者同士で作成することもできますが、可能であれば公正証書にしておくことを強くおすすめします。公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書であり、高い証明力と強制執行力を持つものです。離婚の公正証書には「万一支払いが滞った場合、直ちに強制執行を受けても異議ありません」という執行認諾条項を付けることができます。この条項があることで、もし元夫が約束した支払いに応じない場合でも、裁判をせずに相手の給与や財産を差し押さえて強制的に履行させる手続きが可能になります。つまり、公正証書にしておけば取り決めを確実に履行させるための法的な担保を得られるわけです。また、公正証書は法律の専門家である公証人が内容をチェックして作成してくれるため、文言の不備や解釈の曖昧さが残りにくいという利点もあります。一度取り決めた約束を将来にわたりきちんと守ってもらうためにも、重要な合意事項は公正証書という形で残しておくと良いでしょう。
専門家に依頼する利点
離婚に伴う取り決めを文書化する際は、当事務所を含めた行政書士に依頼することを検討してください。行政書士は離婚協議書のような法律文書の作成に精通しており、適切な条項の盛り込み方や法的に有効な書式についてアドバイスしてくれます。
プロに任せれば迷うことなく書面を整えることができます。公正証書を作成する場合でも、行政書士が事前に案文を作成し、公証役場での手続きをサポートしてくれます。多少の費用はかかりますが、それ以上に離婚後の生活の安定を確保するメリットは大きいでしょう。どういった内容を取り決め、どのように書面に残すべきか迷ったときは、お一人で抱え込まずにぜひ専門家に相談してみてください。
【関連記事】
>公証役場で離婚協議書を公正証書にする費用は?
40代の離婚に伴う契約書や公正証書はお任せください
![]()
当事務所では、これまでに数多くの離婚に関する契約書や公正証書の作成を通じて、40代を中心とする専業主婦や子育て世代の女性の新たな生活設計を法的にサポートしてまいりました。
「離婚を選んだものの、40代から再スタートできるか不安」「仕事のブランクが長く、経済的な自立がすぐにできそうにない」「今後の生活費や養育費についてしっかりと取り決めておきたい」など、離婚後の暮らしに関わる多様なお悩みに寄り添い、実際に文書を通じて安心を形にしてきた実績がございます。当事務所のネット口コミは150件を超え、総合評価は5点満点中4.9と高い評価をいただいており、丁寧な対応と正確な書類作成への信頼を多くのお客様から寄せられています。
特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
- 40代での離婚後、今後の仕事と生活設計に不安がある
- 離婚後に仕事を探す間の生活費をどうやって確保すればよいか悩んでいる
- 子どもを育てながら、40代からの再就職がうまくいくか心配
- 夫との話し合いで、養育費や財産分与の条件に不公平を感じている
- 慰謝料や年金分割について、書面で正しく残しておきたい
- これまで専業主婦だったため、離婚後の法的手続きや契約に自信がない
こうした悩みをひとつずつ丁寧に整理し、将来にわたって有効な契約書をお作りすることが、私たち行政書士の役割です。離婚は終わりではなく、新しい人生の出発点です。法的な備えをしっかりと整えて、前を向けるよう、どうぞ当事務所にご相談ください。
サービスの特徴
- きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。 - 柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。 - 明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。 - 全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。
離婚協議書作成の流れ
- 初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。 - 契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。 - 協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。 - 協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。 - 協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| ⑴離婚協議書の作成と製本 | 44,000円 | 離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。 |
| ⑵離婚公正証書の作成サポート (上記⑴を含みます。) | 77,000円~ | 離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。 |
※)上記金額に実費がかかります。
当事務所にお任せいただくメリット
- 安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。 - 時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。 - トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。 - 専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。
お問い合わせ
離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
お客様の声
お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。
![]()
40代専業主婦が離婚後に直面する「仕事選び」-よくある質問
Q.40代で専業主婦から再就職するのはやはり難しいのでしょうか?
A.難しさはあるものの、まったく不可能ではありません。40代で離婚した女性の多くは、仕事からしばらく離れていたことによる不安を抱えていますが、近年は未経験者やブランクのある人を受け入れる企業も増えてきています。生活のために働くのではなく、自分の人生を再構築する手段として「働くこと」を前向きに捉えることが大切です。
Q.どのような職種が40代の離婚経験者に向いていますか?
A.飲食業や販売業などの接客分野、清掃や軽作業といった未経験でも始められる職種が多く見受けられます。介護業界は特に人手不足が続いており、年齢に関係なく受け入れられやすい分野です。また、事務職もスキルがあれば派遣で採用されやすい傾向があります。
Q.離婚を機にパートと在宅のダブルワークをしたいのですが、問題はありますか?
A.ダブルワークは収入を安定させる手段として有効ですが、無理のない働き方を心がけましょう。特に40代で離婚したばかりの時期は、身体的にも精神的にも負担をかけすぎないように注意が必要です。在宅ワークを副業としてスタートする方も多く、まずは小さな一歩から始めるのが賢明です。
Q.40代で離婚して扶養から外れた場合、すぐに社会保険の手続きをしないといけませんか?
A.はい、速やかに手続きする必要があります。離婚と同時に配偶者の扶養資格を失いますので、国民年金と国民健康保険への加入を早めに行ってください。未手続きのままでは医療費の全額負担や将来の年金額に影響する可能性があります。
Q.40代で離婚した後の生活費が心配です。何を取り決めておくべきですか?
A.離婚時には、今後の経済的不安に備えて「財産の分け方」や「子どもの費用負担」などを話し合い、合意内容をきちんと記録することが重要です。元配偶者から生活支援として一定額の支払いを受ける取り決め(扶養的分与)も検討するとよいでしょう。
Q.養育費はいつまで受け取れるのですか?
A.養育費は一般的に、子どもが成人または大学を卒業するまで受け取るのが基本です。ただし、具体的な期間や金額は双方で取り決めておく必要があります。支払い方法や途中で見直す条件も明記しておくとトラブルを防げます。
Q.離婚の慰謝料を請求するにはどうすればよいですか?
A.不貞行為や暴力など、精神的な被害を受けた場合は慰謝料の対象になります。離婚時の話し合いで金額や支払い方法を決め、文書化しておきましょう。後に支払いが滞ることが心配な場合は、公正証書にしておくと強制的に履行させる手続きが可能です。
Q.年金分割とは何ですか?40代の私にも関係ありますか?
A.年金分割とは、婚姻期間中に配偶者が積み立てた年金の一部を、離婚後に自分の年金として受け取れる制度です。40代の離婚でも、将来の年金に関わる重要な権利ですので、必ず忘れずに手続きを進めてください。離婚から2年以内に届出が必要です。
Q.離婚の取り決めは口約束でも大丈夫ですか?
A.口約束は証拠にならず、後々トラブルのもとになります。特にお金や子どものことに関する話し合いは、必ず離婚協議書や合意書として書面にまとめましょう。金銭が絡む内容については、公正証書にすることで強制力が高まり安心です。
Q.離婚協議書や公正証書の作成は自分でできますか?
A.作成そのものは可能ですが、内容に不備があったり、法的効力を持たせる文言が不足していたりすると意味をなさないことがあります。不安がある場合は、行政書士に依頼して適切な文面に整えてもらうのがおすすめです。当事務所でも文案作成から公証役場との連携まで丁寧にサポートしています。
40代専業主婦が離婚後に直面する「仕事選び」-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、40代女性の離婚後の仕事選びで直面する課題とその対策について行政書士の視点から解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
1.再就職の現実と受け入れられやすい仕事
40代で離婚し働き始めるには、年齢や空白期間が大きな壁になります。採用においては即戦力が重視されるため、未経験職種では苦戦することも。とはいえ、未経験歓迎のパートや派遣、介護・販売・軽作業といった求人も増えてきています。年齢よりも人柄や姿勢が評価される分野を見極めることが鍵となります。
2.扶養喪失後に生じる社会保険の負担
離婚すると、夫の扶養から外れることにより健康保険や年金の手続きを自分で行う必要が生じます。国民年金や国民健康保険の保険料は自己負担となり、月々の支出が増えるため注意が必要です。家計の見直しや収入確保、支援制度の活用を早めに考えておくべきです。
3.副業やフリーランスも選択肢に
会社勤めだけでなく、自宅でできる在宅ワークや副業で収入を得る方法もあります。ライティングやネット販売、講師業などは始めやすく、パートと組み合わせることで安定も図れます。ただし、健康や育児とのバランスには配慮が必要です。自分の得意分野を活かし、少しずつ実績を積むことが現実的です。
4.生活を守る契約の取り決め
離婚後の生活を安定させるには、離婚時の取り決めをきちんと書面に残すことが不可欠です。
- 財産分与では預金・不動産・退職金などを公平に分ける
- 養育費は金額や支払い方法を明確にしておく
- 不貞や暴力による慰謝料も合意があれば記載
- 年金分割は老後資金を支える大切な制度
これらの内容は離婚協議書に記載し、公正証書としておくことで、後の支払い不履行にも強く対応できます。
5.専門家に相談するという選択
行政書士に依頼すれば、文書作成から公証役場手続きまで一貫してサポートを受けられます。迷ったときは一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することが安心への近道です。
【政府の記事】
>令和4年度「離婚に関する統計」の概況
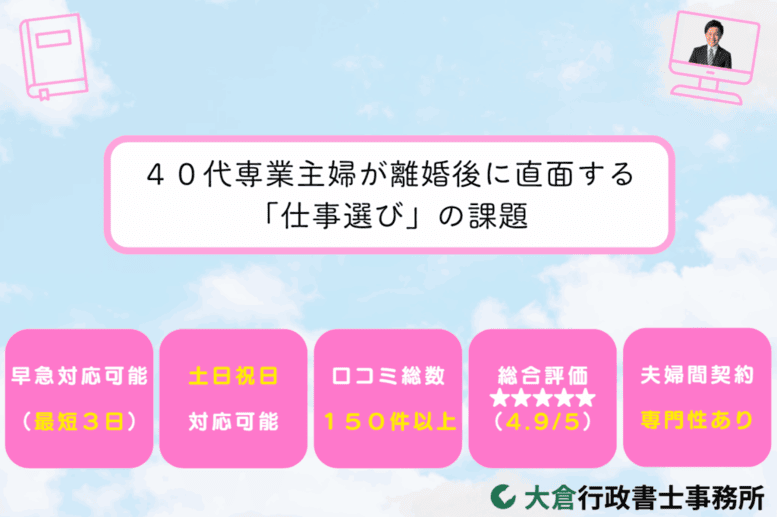


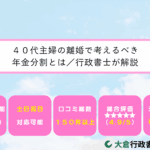
コメント