離婚後の養育費をきちんと受け取れるか不安に感じていませんか?日本では、実際に養育費を受け取っている家庭は全体の2割程度とも言われ、約8割のケースで養育費が支払われていないのが現状です。
養育費未払い問題の背景には、離婚時に養育費の取り決めをしていない(厚生労働省の調査では約4割しか取り決めがなされていません)場合が多いこと、あるいは取り決めをしていても強制的に支払わせる手続きが難しかったことがあります。
離婚協議書という形で養育費を約束していても、相手が支払いを怠れば、これまでは公正証書や裁判所の調停調書などの債務名義がない限り、給与の差し押さえといった強制執行をすぐに行うことはできませんでした。
その結果、養育費の未払いによって子どもの生活や教育に必要な費用が確保できず、ひとり親世帯の貧困につながる深刻な問題にもなっています。しかし、最近の民法改正によって状況が大きく変わろうとしています。
今回の民法改正(2024年)では、離婚協議書など私的な合意書に基づいて債務名義がなくても相手の財産を差し押さえられる新ルールが導入されます。それだけではなく、離婚時に養育費を決めていなくても一定額を請求できる「法定養育費」の制度も新設され、さらに養育費に関する裁判手続きもスムーズになるよう見直しが行われました。
本記事では、民法改正による新制度の内容とポイントを詳しく解説します。離婚協議書があれば養育費の差押えが可能になる仕組みとその背景、改正前との違い、「法定養育費」とは何か、そして養育費を確実に受け取るために離婚時に何をすべきかなど行政書士の視点からわかりやすく説明します。
それでは、今回の制度変更で何が可能になったのか、詳しく見ていきましょう。
改正のポイント
|
離婚協議書で養育費の差押えが可能になった背景とポイント
![]()
この章では、民法改正によって離婚協議書(養育費の合意書)がどのように強力な効力を持つようになったか、その背景とポイントを説明します。2024年5月に養育費等に関する民法改正法が成立し、遅くとも2026年5月までに施行される予定です。
この改正により、養育費の支払い確保を目的とした画期的な仕組みが導入されました。ポイントは養育費債権への「先取特権」付与によって、離婚協議書など夫婦間の合意文書が強力な効力を持つようになったことです。以下で詳しく見ていきましょう。
養育費債権への先取特権が新設される
民法改正の最大のポイントの一つが、養育費債権に対する先取特権の新設です。先取特権とは、特定の債権を他の債権に優先して弁済を受けられる権利のことで、今回の改正により養育費がこの対象に加わります。
これにより、養育費の取り決め(合意)が親同士で行われていれば、裁判所の判決や公正証書など正式な債務名義がなくても、相手の財産に対して差押えを申し立てることが可能となります。
つまり、離婚協議書など当事者間の合意文書があれば、相手の給料や預貯金などを法的手続によって差し押さえて養育費を回収できるようになるのです。裁判所の判決がなくても、いきなり差押えができるという非常に強力な権利と言えるでしょう。
さらに先取特権があることで、仮に相手に他の借金があった場合でも、養育費の債権者(養育費をもらう側)が他の一般の債権者よりも優先して相手の財産から回収できるメリットもあります。
なお、民法上で複数の先取特権が競合した場合の優先順位も定められており、養育費の先取特権は労働者の賃金など雇用関係の債権に次ぐ順位とされています。それだけ子どもの養育費回収が社会的に重視されたということができるでしょう。
公正証書なしでも給与の差し押さえ申立てが可能に
従来、養育費の支払いを法的に強制するには、公正証書(強制執行認諾文言付き)や調停調書・審判書・判決書といった公的な書面=「債務名義」が必要でした。
単なる離婚協議書(私文書)だけでは法的強制力がなく、相手が養育費を支払わない場合はまず家庭裁判所で養育費請求の調停を起こし、債務名義を取得しなければ給与差押え等の強制執行ができなかったのです。
今回の改正では、この「債務名義」に代わるものとして「その存在を証する文書」を裁判所に提出することで差押えを申し立てることが可能になります。平たく言えば、父母の間で作成した離婚協議書などの合意書を証拠として裁判所に出せば、相手の給与や預金口座を差し押さえる手続きができるいうことです。
例えば、離婚協議書に「毎月○万円の養育費を支払う」と明記していれば、支払いが滞った際にその協議書を裁判所に提出して相手の給与や預金の差し押さえを求めることが可能です。煩雑な調停や裁判を改めて起こさずに済む分、迅速かつ低コストで養育費の回収手続きに移れるようになる点は大きな利点と言えます。
差押えを確実に行うための注意点(合意書作成時のポイント)
離婚協議書に基づいて差押えが可能になるとはいえ、どんな書面でも無条件に認められるわけではありません。裁判所に合意書を提出する際、それが当事者間で真正に合意された内容であることが明確でなければ、先取特権による差押えの効力が認められない恐れがあります。
確実に差押えを行うため、離婚協議書(養育費合意書)作成時には次のポイントに注意しましょう。
- 当事者の署名・押印
支払義務者(養育費を支払う側)の意思に基づく合意であることを証明するため、必ず本人の署名と押印をもらいます。可能であれば実印を用い、印鑑証明を添付すれば書面の信頼性が高まります。 - 当事者の特定
誰と誰の間の取り決めかが一目で分かるよう、当事者双方の氏名・住所を明記します。一方が作成した念書のような形式で相手の名前が記載されていない場合、裁判所に提出しても「対象者が特定できない」と判断され無効になるリスクがあります。 - 支払い内容の明確化
養育費の合意内容は金額だけでなく、「いつから支払いを開始し、いつまで支払うのか」「支払日・支払方法(例:毎月〇日までに指定口座へ振込)」などを具体的に定めます。強制執行で差し押さえをするには未払い額を確定する必要があるため、期間や支払期日が曖昧だと回収できる金額が判断できず、申立てが認められない可能性があります。
以上の点を踏まえ、離婚協議書はできるだけ詳細かつ明確に作成することが重要です。せっかく新しい制度で権利が認められても、書面不備のせいで「効力なし」とされてしまっては元も子もありません。
専門家のアドバイスを受けながら不備のない協議書を作成しておけば、いざというとき先取特権による差押え手続によって確実に養育費を回収できるでしょう。
改正前は離婚協議書だけでは養育費の差押えができなかった
次に、民法改正前の制度ではなぜ離婚協議書だけで養育費の強制執行(資産差押え)ができなかったのか、その理由と問題点を整理します。過去の制度では私的な合意だけでは不十分で、必ず公的な手続きを経て債務名義を取得しなければ強制執行が認められませんでした。
ここでは、改正前に必要だった手続きや債務名義の役割、そして養育費未払いへの対処が困難だった現実について解説します。
差押えには債務名義が必須だった
改正前の法律では、養育費を強制的に取り立てるためには債務名義が不可欠でした。債務名義とは支払い義務の存在と内容を公的に証明する文書のことで、具体的には裁判所の判決書、調停調書、和解調書、あるいは公証役場で作成する公正証書(強制執行認諾文言付き)などが該当します。
離婚協議書は夫婦間の合意を書面化したものに過ぎないため、それ自体には法的強制力がなく、相手が養育費を支払わない場合にはまず家庭裁判所で養育費請求の調停を起こし、債務名義を取得する必要がありました。
公正証書にしておけば離婚協議書がそのまま債務名義となり、養育費の不払い時には直ちに強制執行(差押え)が可能でした。しかし、公証役場で公正証書を作成するには手数料がかかりますし、夫婦双方が出向いて手続きを踏まねばなりません。
費用負担や心理的ハードルから公正証書化しない夫婦も少なくなく、その場合は結局、後日養育費の不払いが起きた際に改めて家庭裁判所で調停を申し立てたり訴訟を起こしたりして判決を得る必要があったのです。単なる私文書である離婚協議書では、裁判所は直ちに強制執行の手続きを認めてくれなかったというわけです。
協議書だけでは不十分だった理由
では、なぜ私的な合意書だけではダメだったのでしょうか。その背景には、養育費支払いトラブルにおける証拠や手続き上の問題がありました。離婚協議書はあくまで当事者間の契約書にすぎず、内容に不備があったり署名が偽造されたりする可能性も排除できません。
裁判所としては、給与や財産の差押えという強力な手段を認める以上、「本当にその支払い義務が存在するのか」を公的に確認するプロセス(調停や審判、裁判)を経る必要があると考えていたのです。
また、協議書の内容が曖昧だった場合、「どの時点からいくら未払いになっているのか」が判然とせず、差し押さえる金額を確定できない恐れもあります。例えば「子どもの養育費について相当の額を支払う」とだけ書かれた合意では、具体的な金額も期間も不明瞭です。
このような場合、裁判所は差押命令を出しようがありません。改正前はこうした理由から、父母の私的な取り決めだけでは養育費を直ちに差し押さえることができなかったのです。
養育費未払いへの対処が難しかった現実
たとえば、離婚協議書で毎月の養育費支払いを約束していたにもかかわらず、相手が突然支払いを滞らせたケースを考えてみましょう。改正前の制度では、すぐに給料を差し押さえることができず、まず家庭裁判所に調停を申し立てて債務名義(調停調書等)を取得するところから始めなければなりませんでした。
その結果、実際に強制執行による回収に着手できるまで長い時間と手間がかかり、その間に監護親(養育費を受け取る側)の経済的負担は一層深刻になります。厚生労働省の調査でも、養育費の取り決めがないケースでは支払い率が著しく低いことが示されており、取り決めがあっても相手が応じない場合に法的手続きを敬遠して泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
実際問題として、養育費の取り決めがあっても支払われないケースは非常に多く、不払いになってから債務名義を取るには時間と労力がかかるため、その間に生活に困窮してしまうシングルマザー・シングルファーザーもいます。
例えば毎月の養育費をあてにしていたのに突然支払われなくなった場合、家庭裁判所に調停を申し立てて結論が出るまで数か月以上要することもあり得ます。その間にも子どもの生活費や教育費は必要ですから、養育費が途絶えればすぐに生活が立ち行かなくなる恐れがあります。
また、運良く判決や公正証書を得ても、相手の勤務先や口座情報が分からなければ差押えすべき財産を特定できず回収不能になる場合もありました。改正前はこのように、離婚協議書で養育費の約束をしていても、不払い時の対処がスムーズにできないという課題があったのです。
法定養育費ってなに?新たに導入された制度の概要
![]()
このトピックでは、改正民法で新設された「法定養育費」とは何か、その概要とポイントを説明します。法定養育費とは、離婚時に養育費について取り決めをしなかった場合でも法律で定められた一定額の養育費を請求できる制度です。
導入の背景には、多くの離婚家庭で養育費の取り決め自体がなされておらず(話し合いが難航したり重要性が認識されていなかったりするため)、その結果子どもの生活が経済的に不安定になる問題があります。
この制度が導入された目的は、離婚後も子どもの基本的な養育費を確保し、健やかな成長を支えることにあります。ここでは、法定養育費制度の内容とメリット・デメリット、支払う側・受け取る側双方の注意点を見ていきましょう。
離婚時に取り決めがなくても一定額を請求できる制度
法定養育費制度が導入されたことにより、父母が養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、離婚後に子どもと一緒に暮らす親(監護親)が相手方に対して法律で定められた一定額の養育費を請求できるようになります。
従来は、養育費はあくまで父母間の協議や家庭裁判所での調停・審判によって具体的な金額を決めなければ請求できませんでした。しかしこの新制度により、離婚時に合意がなかったとしても子どもの権利として最低限の養育費を受け取れる道が開けます。
法定養育費の請求権は改正民法施行後に離婚した場合にのみ発生し、言い換えれば改正施行後の離婚には離婚と同時に自動的に法定養育費の支払い義務が生じる仕組みです。例えば離婚届を提出して正式に離婚が成立した後、もし養育費についての取り決めがなければ、その日以降監護親は相手に法定養育費の支払いを求めることができます(相手に支払い能力があることが前提)。
この制度は、養育費の取り決めをしなかったことで「子どもが養育費を一切受け取れない」という事態を防ぐためのセーフティネットと言えるでしょう。なお、この法定養育費制度が適用されるのは改正法施行後に離婚した場合のみです。施行前に離婚したケースでは法定養育費は発生しませんので、その場合は従来どおり父母間での協議や家庭裁判所で養育費額を定める必要があります。
法定養育費の金額と支払期間
法定養育費として請求できる金額は、今後法務省令で定められることになっていますが、子どもの最低限度の生活を維持するための標準的な費用を基準として算定される比較的低額な水準になる見込みです。
2025年8月時点の報道では月額2万円程度という案が示されているようで、今後パブリックコメント(意見募集)を経て正式に決定される予定です。大幅に高額なものではなく、子どもの基本的な生活費の一部を賄う程度の額と考えられます。支払いの期間については、離婚の日から法定養育費の支払義務が発生し、そこから以下のいずれか早い時点まで毎月支払うことになります。
- 父母が正式に養育費の取り決め(合意)をした日
- 家庭裁判所で養育費に関する審判が確定した日
- 子どもが18歳に達した日(成年に達する時)
つまり法定養育費は、「正式な養育費の取り決めがされるまで」または子が成人するまでの暫定的な制度です。長くとも子どもが18歳になるまで(※成年年齢が18歳となったため)しか受け取れません。
ただし、子どもが大学等に進学する場合などには、親同士の協議で18歳以降も(例:22歳まで)養育費を支払う取り決めをするケースもあります。また、途中で親同士がきちんと協議して養育費の額を決めれば、その時点で法定養育費の支払いはストップします。法定養育費はあくまでも養育費の取り決めがなされるまでの暫定的・補充的な措置であり、子どもの最低限の生活を支えるための制度です。
支払う側・受け取る側の注意点
法定養育費制度は子どもにとって最低限の経済的支えを提供する有益な制度ですが、支払う側・受け取る側それぞれに注意すべき点があります。まず受け取る側(監護親)にとって重要なのは、法定養育費に頼りきりにしないことです。
法定養育費はあくまで画一的に定められた最低額であり、各家庭の状況に応じた十分な額とは言えない可能性があります。そのため、できるだけ早期に父母間で話し合い、互いの収入や生活状況に見合った適正な養育費の額を合意して取り決めることが望ましいでしょう。
実際、法定養育費は子どもの生活費の一部にとどまりますので、子どもの将来のためには各家庭ごとに柔軟な対応が必要です。
一方、支払う側(別居親)にとっては、収入が乏しくても一律に支払い義務が生じる点に注意が必要です。法定養育費の額は支払う親の収入事情を考慮せず定められるため、場合によっては従来の算定表で算出する養育費より高額になる可能性もあります。
ただし、改正民法では救済規定も設けられており、支払義務者が支払い能力を欠いていて養育費を支払うことができない場合や、その支払いによって自らの生活が著しく窮迫してしまう場合には、必要な証明をすることで法定養育費の全部または一部の支払いを拒むことが可能です(生活保護受給中などが典型例でしょう)。
家庭裁判所は事情に応じて養育費の支払いについて免除や猶予など適切な処置を命ずることもできます。このように支払う側にも配慮された仕組みにはなっていますが、離婚時に何も決めずにいると「法律で一方的に決められた額」を支払わなければならないリスクが発生します。支払う側にとっても不意の負担とならないよう、やはり離婚時にきちんと話し合いをして養育費を取り決めておくことが重要と言えるでしょう。
養育費を確実に受け取るために大切なポイント
このトピックでは、改正後の新しい制度も踏まえつつ、養育費を確実に受け取るために押さえておきたいポイントを解説します。法律が整備されても、最終的に子どもの生活を守るためには親の協力と適切な手続きが不可欠です。
ここでは、離婚時に必ず養育費の取り決めを行う重要性、離婚協議書を作成するメリット、そして万が一養育費が滞った場合の対処法について説明します。
離婚時に養育費の取り決めを必ず行う
養育費の未払い問題を防ぐ第一歩は、離婚時に必ず養育費について話し合い、取り決めをしておくことです。離婚時は感情的な対立や経済的な不安から、養育費の話し合い自体が十分にできずに終わってしまうこともあります。
しかし、養育費の約束をあいまいにしたまま離婚してしまうと、後から請求するのは困難になり、子どもの生活に支障が生じる恐れがあります。厚生労働省の調査でも、養育費の取り決めをしていないケースでは支払い率が著しく低いことが示されています。
忙しさや気まずさから養育費の話題を避けてしまう夫婦もいますが、子どもの健やかな成長のためには、離婚時に将来を見据えて双方が合意できる養育費額を決めておくことが大切です。改正民法の下では、離婚時に合意がない場合には法定養育費が自動的に発生する仕組みになりましたが、裏を返せば「何も決めずにいると法律で定められた額を払うことになる」ということでもあります。支払う側・受け取る側双方にとって後の紛争を防ぐため、必ず協議離婚の際に養育費の取り決めをしましょう。
離婚協議書を作成するメリット
口頭の約束だけでは後で「言った・言わない」の争いになる恐れがあるため、養育費の取り決めは必ず書面(離婚協議書)に残すようにしましょう。離婚協議書を作成するメリットはいくつもあります。
まず、合意内容を明確に証拠として残せることで、支払いが滞った際に相手に履行を求めやすくなります。特に今回の改正によって、離婚協議書が強制執行の場面で大きな威力を発揮するようになりました。
ただし、その効力を十分発揮させるためには前述のとおり内容を明確にし形式を整える必要があります。インターネット上の雛形(テンプレート)を使って自分で作成することも不可能ではありませんが、重要な条項の漏れや文言の不備があると後々トラブルになる可能性があります。
不安がある場合は専門家(行政書士等)に相談し、漏れのない離婚協議書を作成することをおすすめします。さらに、可能であれば離婚協議書を公正証書化することも検討しましょう。
公正証書に強制執行認諾文言を付しておけば、改正施行前であっても養育費の不払い時にただちに強制執行手続きが可能となりますし、改正後も確実な債務名義として機能します。公証役場での手続きには多少の費用がかかりますが、相手に支払いを促す強いプレッシャーにもなります。
養育費が滞ったときの対処法
万が一、約束した養育費が支払われなくなってしまった場合でも、慌てず適切に対応すれば回収できる可能性があります。まずは電話やメールなどで相手に支払いを催促し、それでも応じない場合には速やかに法的手続きに移行することが重要です。
改正後は離婚協議書(または公正証書)があれば、家庭裁判所での調停を経ずに地方裁判所に直接差押えの申立てをすることができます。申立ての際には未払いとなっている養育費の計算書(支払期限ごとに未払い額を算出した一覧)や離婚協議書の原本などを用意しましょう。
相手の勤務先や銀行口座など差し押さえるべき財産に関する情報が分からなくても大丈夫です。改正民事執行法では、裁判所に1回の申立てをするだけで次のような一連の措置を求めることが可能になりました
- 相手方に自身の財産内容を開示させる「財産開示手続」
- 市区町村など第三者から相手の勤務先情報や収入情報を取得する「第三者からの情報提供命令」
- 判明した給与債権や預貯金債権を差し押さえる「債権差押命令」
さらに、裁判所からの財産開示命令に相手方が従わず正当な理由なく情報提供を拒んだり虚偽の申告をした場合には、10万円以下の過料(科料)に処せられる可能性もあります。
これにより、「相手の収入や財産がつかめず差し押さえできない」といった事態も起きにくくなっています。実際に差し押さえが認められれば、相手の給料から毎月一定額(養育費の場合は手取りの最大1/2まで)を直接回収することができます。
なお、強制的な手続き(差押え)に訴える前に、ケースによっては再度話し合いで解決を図ることも検討しましょう。例えば相手に収入減少など支払えない事情が生じた場合には、養育費の金額や支払方法の見直しを協議することも必要です。
一方で支払能力があるのに悪質に滞納している場合は、早期に法的措置を取ることで未払いが嵩むのを防ぐべきです。
養育費は親に課せられた法的義務であると同時に、子どもの大切な権利です。以上、民法改正による養育費に関する新制度と、離婚協議書をめぐるポイントについて解説しました。
今回の改正で、離婚協議書という合意書があれば養育費の差押えができるようになるなど、養育費を取り巻く環境は大きく前進します。しかし最も大切なのは、親同士が子どものためにきちんと向き合い、適切な養育費を取り決めて履行することです。この基本となる話し合いや合意のステップをおろそかにせず、お子さんの将来を守るためにできる限りの手当てをしておきましょう。
なお、改正法の施行時期は2026年5月までに予定されていますが、現時点では具体的な日程は未定です。また、法定養育費の金額や先取特権による差し押さえの範囲など細部は今後政省令で定められる予定です。最新の情報を確認しつつ、新制度を適切に活用していくことが大切です。
離婚協議書の作成は当行政書士事務所にお任せください
![]()
養育費の取り決めや離婚協議書の作成に不安がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、離婚協議書の作成支援を数多く手がけており、公正証書化の手続きについても依頼いただけます。
行政書士は、あなたの事情に合った協議書作成や手続きについてアドバイスし、子どもの未来を守るお手伝いをしてくれるはずです。専門家の力も借りながら、子どものために最善の養育費の取り決めと履行を実現していきましょう。
サービスの特徴
きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
全国対応
当事務所は奈良県生駒市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については大阪府、兵庫県などの近畿圏を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。
離婚協議書作成の流れ
- 初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。 - 契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。 - 協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。 - 協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。 - 協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。
料金
| サービス | 料金(税込) | 概要 |
|---|---|---|
| ⑴離婚協議書の作成と製本 | 44,000円~ | 離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。 ご希望に応じて公正証書への移行サポートも可能です。 |
| ⑵離婚公正証書の作成サポート (上記⑴を含みます。) | 77,000円~ | 離婚公正証書の原案作成をサポートさせていただきます。 代理調印の有無などにより費用が異なります。 |
※上記金額に別途、実費(郵送料・公証人手数料等)がかかります。
当事務所にお任せいただくメリット
- 安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。 - 時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。 - トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。 - 専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。
お問い合わせ
離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
お客様の声
お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。
![]()
【政府の記事】
日本年金機構「離婚時の年金分割」
法務省「年金分割」
法務省「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」
厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」


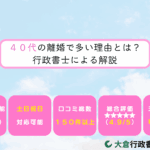
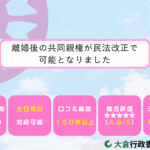
コメント