離婚後のお子さんの養育について、「養育計画書」(実務では「養育契約書」と呼ぶこともあります)を作成する動きが広がっています。2024年成立の民法改正(遅くとも2026年まで施行)により、離婚後も共同親権を選択できる見込みとなりました。
これからは父母が離婚後の親権を共同親権にするか単独親権にするかを協議して決める時代です。同時に、離婚時には養育費や面会交流(親子交流)など子の養育に関する事項をしっかり取り決め、子の最善の利益を最優先に考慮することが求められます。こうした背景から、離婚時にお子さんの将来のための詳細な計画を取り決め書面に残す養育計画書の重要性が増しています。
本記事では、共同親権時代を見据えた養育計画書の意義や作成手順(5ステップ)、盛り込むべき具体的な条項とそのポイントを解説します。
さらに、実務でそのまま使える条項テンプレート(ひな形)も掲載しました。離婚を準備・協議中の方が正確で使える情報を得て、ご自身のお子さんのために最適な養育プランを策定できるようサポートします。
当事務所(行政書士)は全国対応・オンライン面談可で、相談から計画書の設計、公正証書化まで伴走いたします(※初回相談無料・料金は後述)。ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考になさってください。
離婚後の子の養育を巡る法改正の背景と共同親権の導入
![]()
近年、離婚後の子どもの養育環境をめぐる法律が大きく見直されました。2024年5月に「父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法」が成立し、子どもの権利利益を守る観点から親権・監護、養育費、親子交流等のルールが改善されています。
この改正の背景には、離婚後も両親が適切に子育てに関わり責任を果たすことが子の最善の利益に不可欠だという考えがあります。
従来の民法では離婚時にどちらか一方を親権者と定める単独親権のみでしたが、従来制度では非親権者となった親との交流や養育費支払いが十分になされないケースが問題視されてきました。また、養育費不払いの多さや親子断絶の弊害が社会問題となり、国としても対策が求められていたのです。
この共同親権導入により、離婚後も両親が子育てに関与し続けるケースが増えると期待されています。一方で、父母双方が親権を持つことで役割分担や意思決定のルールを明確に決めておかなければ、かえって紛争の火種となるリスクも指摘されています。
そこで注目されているのが「養育計画書」の活用です。共同親権・単独親権を問わず、離婚時に子の養育について細かな取り決めを書面化しておくことは、後々のトラブル防止に非常に有効だとされています。
養育計画書の意義と役割(子の利益を最優先に)
養育計画書とは、夫婦が離婚(または別居)する際に、子どもの養育に関する事項を父母間で合意し文書化した契約書です。
具体的には、離婚後のお子さんの養育費の支払方法、生活や教育方針、しつけのルール、面会交流(親子交流)の頻度や方法など、子育てに関する取り決めを詳細に記載します。
養育計画書を作成する最大の目的は、両親の離婚後の子育てにおける将来の紛争を防止することにあります。口頭の約束だけでは後で「言った/言わない」のトラブルになりがちですが、文書にしておけば証拠となり履行の担保にもつながります。
また、お子さんにとっても、両親が離婚後の生活についてしっかり話し合い合意していることは安心材料となります。養育計画書は子どもの健やかな成長を両親で支えるための「共同養育契約書」とも言えるでしょう。
ポイントは、養育計画書が法律上必須の書面ではないものの、作成が強く推奨される点です。現行法でも未成年の子がいる協議離婚では養育費と面会交流について取り決める努力義務が課されています。
しかし実際には、それらを具体的に決めず離婚してしまう夫婦も少なくありません。その結果、離婚後に「養育費を払ってもらえない」「子どもに会わせてもらえない」といった深刻なトラブルが生じがちです。養育計画書を交わしておけば、そうした養育費不払いや親子断絶のリスクを下げ、問題発生時も合意内容に立ち戻って解決を図れます。
子の最善の利益を最優先に-計画作成の基本理念
![]()
養育計画書を作成する際に何より重要なのは、子どもの最善の利益を第一に考えることです。離婚は夫婦の事情であっても、その後の生活を左右される子どもにとっては大きな出来事です。計画書の内容は、親の都合や感情ではなくお子さんの幸せや健やかな成長を基準に決めましょう。
例えば、面会交流の頻度や方法については、子どもの年齢や気持ちに配慮し「どのような交流が子にとって望ましいか」の視点で具体的に決めます。
養育費の金額も、親の負担感だけでなく子どもの生活水準維持と将来の教育に必要な費用を軸に考慮します。親同士が対立してしまうと話し合いが難航しがちですが、「この内容は子の利益になるか?」と自問することで冷静に合意点を見出しやすくなります。
加えて、共同親権を選択する場合は特に、父母双方が子育てに関与する前提となるため、協力体制を築くことが不可欠です。計画書作成のプロセス自体が、離婚後の共同養育の第一歩になります。お互いの役割分担や連絡方法を取り決める中で、両親がチームとして子育てに向き合う意識を共有する効果も期待できます。
仮に単独親権の場合でも、もう一方の親が子育てに関わり続ける意思があるなら、可能な範囲で交流や情報共有のルールを決めておくと良いでしょう。いずれにせよ、「子どもが両親の愛情を感じながら成長できるようにする」ことが計画書の理念です。
養育計画書の作成手順(推奨5ステップ)
ステップ1.現状把握
まずは家族の現状と課題を整理することから始めます。お子さんの年齢・性格・生活環境、居住予定、両親それぞれの収入・仕事状況、居住地の距離感など、離婚後の養育に影響する要素を書き出します。
例えば「子どもはまだ幼いため頻繁な面会交流は難しいのでは?」とか「父は出張が多いので養育費の支払方法は銀行振込が確実」など、状況に応じた考慮点が見えてくるでしょう。あわせて現在夫婦間で合意できている事項・意見が対立している事項を洗い出し、話し合うべき論点を明確化します。
ステップ2.論点抽出
現状整理を踏まえ、養育計画書に盛り込むべき論点リストを作ります。典型的な論点としては以下のようなものがあります。
- 親権者:共同親権にするか、単独親権なら父と母どちらにするか
- 監護権者:親権とは別に監護権(普段の世話・養育担当)をどちらが持つか
- 住居:子どもの居住地(主たる生活拠点)をどこに定めるか
- 養育費:金額、支払方法、支払期間、特別費用の分担方法、滞納時の対応
- 面会交流:頻度(例:月◯回)、1回の時間、場所、宿泊の可否、連絡手段、送り迎え方法、ルール
- 重要事項の決定方法:進学先や転居、手術など重要な判断をどう協議するか
- 情報共有:学校からの連絡や成績表、病院の診療情報などをどう共有するか
- 緊急時対応:病気・災害など緊急時の連絡方法や引き取り方法
- 違反時の対応:約束が守られない場合の話し合い方法、調停利用など
- 定期見直し:計画の見直しタイミング(例:年1回)や変更手続き
ご家庭によっては他にも、習い事や宗教行事への参加、祖父母との交流、生命保険の受取人指定など細かな論点が出てくるかもしれません。ステップ2では漏れなく論点をリスト化し、優先順位も付けておきます。
特に重要で複雑な論点(例えば親権者や居住地、養育費の額など)は時間をかけ丁寧に話し合う必要がありますので、次のステップ以降で重点的に検討します。
ステップ3.条項設計
抽出した各論点について、具体的な取り決め内容(条項案)を設計していきます。法務省のパンフレット等も参考に、子の利益に沿った合意例を考えます。
この段階ではまだ夫婦間で完全合意していなくても構いません。まずはたたき台として、「養育費は公的算定表を参考に月◯万円」「面会交流は月2回、第三者機関で引き渡し」「重要事項は原則双方合意が必要」等、それぞれ条文化してみます。
ポイントは、条項をできるだけ具体的かつ明確にすることです。「適宜協力する」「柔軟に対応する」など抽象的表現はトラブルの元なので避け、日時・数値・頻度など定量的に記載できる部分は数値で定めます。また将来の変化に備えたい事項については、「○○の場合には協議して変更できる」といった条件付きの文言を入れておくと柔軟性を確保できます。
ステップ4.文案化(ひな形作成)
ステップ3で設計した条項案を基に、養育計画書の文案(ドラフト)を作成します。一般的な契約書形式に従い、契約当事者(父母)や子の氏名、生年月日を明記した上で、第◯条、第◯条…と箇条書き形式で条項を並べます。
文案作成時には形式要件にも注意しましょう。不安な場合は行政書士など専門家に文案のチェックを依頼することも検討してください。
また、文案段階で別表(添付資料)の作成も行います。典型例としては、面会交流の具体的日程を一覧にした「交流スケジュール表」や、特別費用負担の内訳表などです。こうした別表を用意すると条項本文を簡潔にでき、後でスケジュール変更する際も別表差替えだけで済む利点があります。
ステップ5.合意締結
文案がまとまったら、いよいよ夫婦間で最終合意を目指します。両者で文案を確認し、必要に応じて修正・加筆していきます。お互い譲れない点もあるでしょうが、何より子どもの利益を最優先に歩み寄りましょう。
以上のように養育計画書作成の流れは、現状把握→論点整理→条項設計→文案作成→合意締結とい5つのステップで進めるとスムーズです。一朝一夕に完了するものではありませんが、お子さんの将来を守る大切なプロセスです。
場合によっては専門家の力も借りながら、焦らず丁寧に進めましょう。それでは次に、養育計画書に実際どのような条項を盛り込むべきか、重要ポイントを具体的に解説します。
養育計画書に盛り込む基本項目
子の重要事項の決定方法に関する取り決め
![]()
離婚後の子育てでは、教育や医療など子の重要事項を誰がどのように決定するかを明確にしておく必要があります。
共同親権の場合は法律上原則両親共同で決めるものですが、単独親権でも計画書で協議ルールを定めておけば双方関与が可能です。
取り決めるべき主な重要事項としては次のようなものがあります。
教育方針・学校選択
どの学校に進学させるか、公立・私立の選択、中学高校受験の有無、塾通いの可否など。計画書には「子の就学先(小中高校)については父母が事前に協議して決定する」等と定めます。特定の宗教系学校への入学是非など価値観が絡む場合は念入りに話し合い、合意内容を書きます。
医療方針
重大な病気や手術を要する場合の判断、予防接種や定期健診の実施など。例えば「手術等の重要な医療行為は父母双方の同意のもとに行う」「緊急時を除き事前にもう一方に連絡する」といった条項が考えられます。
居所・転居
子どもの住む場所を変更する(引っ越しする)場合の扱いです。監護親が遠方に転居すると面会交流等に影響するため、「子の住所を変更する際は事前に相手方へ通知し同意を得る」としておくと良いでしょう。
少なくとも「○○市外へ転居する場合は事前協議する」など範囲を決めて同意事項にすると安心です。
海外渡航
子どもを海外旅行・留学させる場合や、親が子を海外に連れて行く場合も取り決めが必要です。国際誘拐防止の観点からも「子を海外に連れ出す際は必ず相手に行き先・期間を事前連絡し同意を得る」旨を記載します。期間が長期なら尚更です。
改姓・改名
離婚に伴い子の姓をどちらにするか(親権者の姓に変更するか等)は離婚届提出時点で決めていますが、将来的に改姓改名する際の同意事項も規定可能です。
上記のような重要事項について、養育計画書では決定プロセスを定めます。基本は「父母が事前に協議し合意の上で決定する」です。
合意に至らない場合の対処も合わせて書いておきます。例えば「協議が整わない場合、家庭裁判所の調停または審判により定めるものとする」と明記します。こうしておくと、意見が対立しても一方的に物事が決められてしまうことを防げます。
共同親権を前提とする場合は、民法上も原則共同決定なので計画書で改めて規定しなくとも良いとも言えます。しかし現実には離婚後別々に暮らしていれば意思疎通が難しいケースもありますから、「具体的に何を協議事項とするか」をリストアップしておく意義は大きいです。
例えば「高校以上の進学先は要協議」「予防接種の種類については母の判断に委ねるが重大なものは協議」など、場合分けしても構いません。大切なのは子どもに関する重要な判断を独断で行わないルールを作ることです。
子どもの情報共有の方法・ルール
離婚後に子どもの様子を把握し続けるには、父母間での情報共有が欠かせません。監護親(子と暮らす親)は、子の近況や学校での成績・健康状態などを非監護親にも適切に伝える努力をしましょう。養育計画書には情報共有の具体的方法と頻度を定めておきます。
共有する情報の範囲
学校関連(通知表、行事予定、進路相談結果)、健康関連(健康診断結果、予防接種履歴、通院治療情報)、生活関連(習い事や部活動の状況、友人関係での大きな出来事)など、共有すべき情報を例示します。「学校からの配布プリントや成績表、病院の診療情報等は取得後速やかに相手方に提供する」という具合です。
共有の手段・頻度
情報提供の方法は、写メ・PDF等でメール送付が一般的です。計画書には「学校からの連絡プリント類は写真またはPDFにてメール送信する」「月に1回、子の生活に関するレポートをメールで送る」などと具体的に書きます。
昨今はLINEグループ等で日々の様子を報告し合う家庭もありますが、形式は夫婦間で無理のないものにしましょう。頻度もあまり頻繁だとかえって負担になり長続きしないため、例えば「学期ごと」「毎月末」といった適度な間隔で約束するのがおすすめです。
学校・園との連絡先登録
監護親でない方の親も学校や保育園に連絡先を登録し、両親とも学校から直接情報提供を受けられるようにする取り決めも有用です。最近は学校が保護者それぞれに連絡メールを配信する仕組みもありますので、「父母それぞれ学校の連絡網に登録することに双方協力する」と記載しておくとスムーズです。
成績表などは本来親権者にしか渡されませんが、コピーを共有する運用でカバーできます。
写真・思い出の共有
子どもの成長の記録(写真や動画)を定期的にもう片方に共有する約束も、お子さんのためには良いでしょう。計画書に「母は子の写真を月1回父に送付する」「運動会等の行事動画はクラウドで共有する」といった一文を入れても構いません。
離れて暮らす親にとって、写真や作品を見るだけでも子どもの成長を実感でき、愛情を伝える手段になります。
緊急時の連絡
子どもに事故や大病など緊急事態が発生した場合は、速やかにもう一方へ連絡する義務があることも盛り込みます。「緊急時には夜間であっても直ちに電話連絡する」など具体的に決めましょう。もちろん普段からの連絡方法を決めていれば自ずと守るでしょうが、念のため明文化しておきます。
情報共有は親同士の協力姿勢を表すものであり、子どものためにも非常に重要です。非監護親にとって、子どもの様子が全く分からない状態は辛く不安になるものですし、それが原因で面会交流を過剰に要求するトラブルも起こり得ます。計画書にて最初から「情報はオープンにする」と決めておけば、双方安心して子育て協力できるでしょう。
ただし守秘すべきプライバシー情報(思春期の子のデリケートな悩み等)は無理に共有せず、子の意思も尊重して柔軟に運用します。
違反時の是正手順と養育計画の見直し条項
最後に、養育計画書にぜひ入れておきたいのが違反時の対応と定期見直しに関する条項です。前者は万一取り決めが守られなかった場合の対処法、後者は時間経過による計画変更の手続を定めます。
違反・紛争時の対応策
計画書のどれかの条項が履行されない、または解釈を巡って争いになった場合の処理方法をあらかじめ決めておきます。一般的な書き方は「父母のいずれかが本合意に反する行為をした場合、まずは速やかに協議して是正策を講じるものとする。協議で解決できない場合、家庭裁判所の調停その他法的手続きにより解決を図ることができる」というものです。
定期的な見直し条項
前述したように、計画は子の成長に合わせて変えていく必要があります。そこで「本養育計画は子の年齢や環境の変化に応じて適宜見直すものとする」という包括的な文言を入れておきましょう。
さらに具体的に、「毎年◯月に父母協議の上、必要に応じて本計画の内容を修正・更新する」と年次レビューを約束する形も有効です。また、臨時の見直しについても書いておきます。
例えば「父または母が再婚した場合」「父母いずれかが子と離れて暮らすことになった場合(単身赴任等)」「子が重大な病気や障がいを負った場合」など、ライフイベントや有事のケースを想定し、その際は速やかに協議して計画の変更に合意できるよう努める旨を記します。
見直しの合意内容は、その都度書面(覚書等)に残すよう計画書で定めておくと、後でどこまで変更合意したか明確にできます。
計画終了後の取り決め
お子さんが成人するなどして養育計画の役目が終わった後に備え、「本計画書は◯◯の時点で効力を失う」とか「終了後の連絡事項は双方プライバシーに配慮し…」等を書いておくケースもあります。
ただ、あまり細かくしすぎる必要はありません。基本的には子どもが成人または計画終了条件に達した時点でこの合意は自然消滅します。
以上、違反時対応と見直し条項について述べましたが、これらは計画を長持ちさせるための保険のようなものです。お互い計画をしっかり守り、適宜話し合って更新していければ理想的です。計画書の作成段階では最悪の場合も想定しつつ、しかし実際の子育てでは良好な協力関係を築いていけるよう努めましょう。
養育計画書には、子の重要事項の決定方法(教育・医療・転居などは事前協議)や、子どもの情報共有方法(学校・健康情報の提供、連絡手段)、そして違反時の協議・調停による解決と定期的な計画見直しといった条項も忘れずに入れましょう。
これらを盛り込むことで、計画書の内容が実践で機能しやすくなり、長期にわたり子どもの利益を守る約束として活きてきます。
養育計画書の実装・テンプレート例とよくある質問
![]()
離婚時にすぐ使える養育計画書の条項テンプレートを以下に掲載します。実務でよく盛り込まれる条項を網羅した雛形ですので、ご自身で作成する際の参考にしてください(※具体的事情に合わせて修正が必要です)。別表として面会交流スケジュールの例も付しています。
養育計画書 令和○年○月○日、父○○○○(以下「父」という)と母△△△△(以下「母」という)は、離婚後の子の養育につき、子□□□(平成○年○月○日生、以下「子」という)が健やかに成長できるよう協力するため、以下のとおり養育計画に合意する。 第1条(親権者・監護者) 第2条(子の居所) 第3条(養育費) 第4条(特別費用) 第5条(親子交流(面会交流)) 第6条(子に関する重要事項の決定) 第7条(子の情報共有) 第8条(計画内容の変更・違反時の対応) |
※ご注意:上記ひな形は一例であり、すべてのご家庭に当てはまるものではありません。個々の状況に応じて条項を取捨選択・修正し、専門家に内容を確認してもらうことを推奨します。
養育計画書に関するよくある質問(FAQ)
Q1.共同親権がまだ施行されていませんが、今のうちから養育計画書を作っておく必要がありますか?
A1.はい、共同親権の有無にかかわらず養育計画書は作成しておくことを強くおすすめします。現行法下でも離婚時に親子交流や養育費を取り決める努力義務がありますし、単独親権で離婚する場合でも後々のトラブル防止のため計画書が有効です。
共同親権制度が開始された後は、二人で子育てするための詳細な取り決めが一層重要になります。制度施行前に離婚する場合でも、「共同親権制度が導入されたら◯◯する」といった将来の条件を盛り込んでおくことも可能です。将来的に制度が変わっても対応できるよう、今から計画書を準備しておくと安心です。
Q2.養育費の金額はどうやって決めればよいですか?
A2.基本的には家庭裁判所公表の養育費算定表を参考にすると良いでしょう。算定表は両親の収入と子の人数・年齢から標準的な月額を示した表です。ただし算定表はあくまで目安ですので、そこからお子さんの特別な教育方針(私立校通学など)やご家庭の事情を考慮して増減を話し合ってください。
双方納得ずくで決めた金額であれば、多少算定表より上下しても構いません。また、一度決めた養育費も長期間の間には物価・収入の変化がありますから、定期的に見直すことも大切です(計画書に見直し条項を入れておきましょう)。
Q4.養育計画書と離婚協議書・公正証書は何が違うのですか?
A4.養育計画書は子の養育に特化した取り決めをまとめた書面です。一方、離婚協議書は夫婦間の離婚条件全般(財産分与・慰謝料・年金分割など含む)を記載する契約書で、養育費や親権についても含みますが項目は多岐にわたります。
公正証書はそれら協議内容を公証人が文書化したものです。養育計画書は法的には離婚協議書の一部と言えますが、特に子どものことにフォーカスして詳細に決めたい場合に別途作成されるケースがあります。実務上、養育計画書を離婚協議書の別紙としたり、公正証書の条項として組み込む形で利用されることもあります。当事務所では離婚協議書(公正証書)作成の際、お客様の希望に応じて詳細な養育計画部分を設計しております。
上記以外にも疑問や不安がありましたら、お気軽に専門家へご相談ください。当事務所の無料相談窓口では、養育計画書づくりに関する質問にも丁寧にお答えしています。
まとめ:養育計画書で“子どもの幸せ”を形に-専門家のサポートも活用を
離婚後のお子さんの生活を守り、両親の協力体制を築くには養育計画書の作成がとても有効です。共同親権時代の到来を控え、国もこの養育プランの作成促進に力を入れ始めています。単なる書面ではなく、そこに込められた「子どもを想う両親の約束」がお子さんの安心と健全な成長を支えるのです。


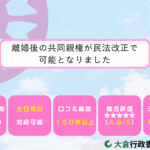
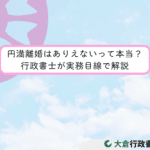
コメント