長年連れ添った夫婦が離婚する「熟年離婚」では、感情面だけでなく財産分与や年金、生活費といった現実的な問題への入念な準備が不可欠です。特に専業主婦の場合、離婚後の経済的な見通しを立てるために、事前にしっかりと情報収集と手配をしておくことが大切です。
また、離婚協議を円滑に進めるためのポイントや、離婚成立後に忘れてはならない各種手続きもあります。本記事では、40代以上の女性・専業主婦を主なターゲットに、熟年離婚を進める際に「やることリスト」として押さえておきたい項目を、行政書士の視点から解説します。後悔のない新生活のスタートのために、ぜひ最後までお読みください。
離婚前に準備しておくこと
![]()
熟年離婚を決断したら、離婚を切り出す前に入念な準備を行いましょう。特に離婚後の生活設計や金銭面のプランニングは重要です。以下では、離婚前に専業主婦の方がやっておくべき準備として、生活費のシミュレーション、財産の洗い出し、そして仕事や住まいの確保について説明します。
離婚後の生活費をシミュレーションする
まずは、離婚後に自分がどのくらいの生活費で暮らしていけるか試算しておきましょう。現在の家計簿や銀行の入出金履歴などを参考に、住居費や食費、水道光熱費、医療費、保険料といった固定費・変動費を洗い出します。
総務省の調査によれば、50代以上の単身女性の消費支出は平均で月15万円前後とも言われます。(参照:家計調査報告「Ⅱ総世帯及び単身世帯の家計収支」)しかし、自分の場合はどうか具体的に計算することが大切です。
将来の年金収入(自身の老齢年金や年金分割による増額分)や、離婚によって受け取る財産分与金額なども見込み、離婚後に不足する生活費がどの程度か把握しておきましょう。生活費のシミュレーションを行っておくことで、離婚後の資金計画に現実味を持たせることができます。
共有財産・負債をリストアップする
次に、夫婦の財産関係を明確にするため、共有財産と負債のリストアップを行います。結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産(預貯金、株式などの有価証券、不動産、自動車、貴金属、生命保険の解約返戻金、退職金の見込み額など)は全て洗い出しましょう。
通帳の残高や証券口座の明細、不動産の登記情報など、証拠となる資料のコピーを手元に確保しておくと安心です。また、住宅ローンやその他借入れがある場合、その残高や名義人を確認します。財産分与の交渉を有利に進めるには、こうした財産・債務の全体像を事前に把握しておくことが重要です。
専業主婦の方は遠慮しがちですが、名義が夫になっている財産でも共有財産であれば妻にも権利がある点を忘れないでください。
【関連記事】
離婚時の住宅ローンの折半は契約書で定めておくべき
離婚後の仕事・住まいを確保する
専業主婦が離婚後に経済的に自立するためには、収入源の確保が欠かせません。離婚前からパートや派遣などで働き口を探し、少しでも収入を得られるよう準備しておきましょう。職業訓練や資格取得の支援制度を活用するのも一案です。
また、離婚後の住居も重要な問題です。持ち家がある場合は、どちらが住み続けるのか、売却して現金を分けるのかを検討します。妻が住み続けるのであれば、名義変更や住宅ローンの引き継ぎといった課題も発生します。
賃貸物件に移る場合は、新居の初期費用や引越し費用も計算に入れておきましょう。離婚後すぐに生活基盤を整えられるよう、仕事と住まいについては早め早めの対応を心がけます。
【関連記事】
熟年離婚したいがお金がない…
離婚協議で決めるべきこと
![]()
準備が整ったら、次は実際に離婚に向けた話し合い(離婚協議)で決めるべき事項を整理しましょう。熟年離婚では特に財産分与や年金分割などお金の問題が中心になりますが、未成年の子どもがいれば親権や養育費、離婚原因に応じて慰謝料の有無も検討します。
ここでは、主に話し合いで決めておきたい事項として、財産分与、年金分割、慰謝料・養育費などのポイントを解説します。
財産分与の内容を決める
離婚時の財産分与は、婚姻期間中に築いた共有財産を夫婦で分ける手続きです。準備段階で把握した財産リストをもとに、どの財産をどちらが取得するかを話し合います。預貯金は原則として半分ずつに分け、不動産はどちらかが取得して代わりに相応の代償金を支払う、あるいは売却して得た代金を分け合う方法が考えられます。
退職金については、在職中の労働に対する後払いの性質がありますが、婚姻期間に対応する部分は共有財産とみなされますので、受給前でも見込み額を考慮して分配を決めましょう。負債がある場合には、夫婦の共同生活のための借金(住宅ローンなど)は財産分与の対象として夫婦で分担し、ギャンブルなど個人的な借金は各自の責任とするのが一般的です。合意が難しい場合は家庭裁判所の調停や審判で判断してもらうことになります。
年金分割と年金に関する取り決め
熟年離婚では、年金分割の取り決めも忘れてはいけません。年金分割とは、夫の厚生年金の納付記録の一部を妻の年金に振り替える制度で、離婚後の妻の老齢年金を増やす効果があります。
話し合いの場で、婚姻期間中の厚生年金記録の何%を分割するか(按分割合)を決めましょう。妻が専業主婦(第3号被保険者)であった期間については法律で定められた按分割合(50%)を請求できますが、それ以外の期間については夫婦間の合意が必要です。
また、年金以外にも、例えば夫が企業年金や共済年金に加入している場合はその取り扱い、離婚後の健康保険の切替え手続き、さらには配偶者として加入していた生命保険をどうするか、といったお金や保障に関する事項も整理しておきましょう。年金分割の請求手続きは離婚後2年以内(法改正により5年以内となりましたが、令和7年6月時点では未施行です。)に年金事務所で行う必要がありますが、スムーズに進めるためにも離婚協議の段階で双方の理解を得ておくことが望ましいです。
【関連記事】
熟年離婚で企業年金はどうなる?
慰謝料や養育費などその他の条件
離婚の際には、財産分与と年金分割以外にも決めておくべき事項があります。まず、離婚の原因が夫の不貞(浮気・不倫)や暴力などの場合、妻から夫へ慰謝料を請求できるケースがあります。
慰謝料を求める場合は、金額(相場は数十万~数百万円)や支払い方法(分割か一括か)を明確に取り決めます。次に、未成年の子どもがいる場合は親権者をどちらにするか、及び子どもを養育しない側の親が支払う養育費の額・支払期間を定めます。
養育費は子どもの将来を左右する大切なお金ですから、公的な算定表を参考に適正な金額を決めましょう。なお、熟年離婚では子どもが既に成人していることも多いですが、その場合でも大学在学中であれば教育費の分担について話し合っておくと良いでしょう。その他、婚姻費用の清算や荷物の引き渡し時期など、離婚に関連する細かな取り決めも忘れずに話し合っておきます。
なお、年金分割により妻の年金がどの程度増えるかは、夫の収入や婚姻期間によって異なります(一般的なモデルケースでは妻の年金が月額数万円増える程度です)。詳細は年金事務所で情報提供を受け確認しましょう。
離婚協議書・公正証書の作成
![]()
離婚条件について夫婦間で合意ができたら、その内容を書面に残します。口頭の約束だけでは後から「言った/言わない」のトラブルになりかねません。特に金銭の支払いを伴う約束は、公正証書にしておくことで万一不履行の場合に強制執行が可能となり安心です。
この章では、離婚協議書に盛り込むべき事項、公正証書化するメリット、そして専門家に依頼する利点について説明します。
離婚協議書に盛り込む内容
離婚協議書(離婚契約書)とは、夫婦間の離婚に関する合意事項を書面化したものです。財産分与や慰謝料、年金分割の割合、養育費の金額・支払終期、親権や面会交流に関する取り決めなど、離婚に関する事項を網羅的に記載します。
日付と双方の署名押印を入れて作成し、夫婦が1通ずつ保管します。離婚協議書を作成しておけば、後になって約束事項を双方で確認でき、万一合意内容に反する事態が生じた際にも証拠となります。
特に熟年離婚では扱う財産額も多いため、書面できちんと残す安心感は大きいでしょう。なお、離婚協議書自体には法的強制力はありませんが、公正証書にすることで強制執行力を持たせることが可能です。
離婚給付契約公正証書の作成とメリット
協議書にまとめた合意内容のうち、金銭の支払いに関する事項(財産分与の支払い、慰謝料や養育費の支払いなど)がある場合は、公証役場で公正証書を作成することを強くおすすめします。
離婚に関する金銭給付の約束を公正証書にしたものを離婚給付契約公正証書と呼びます。公正証書には強制執行受諾条項(約款)を付すことができ、これを付けておけば相手が支払いを履行しないときに直ちに財産差押え等の強制執行手続きを取ることが可能です。裁判で改めて勝訴判決を得る手間が省けます。
公正証書を作成するには夫婦双方が公証役場に出向き、公証人の面前で署名する必要がありますが、行政書士等に依頼すれば手続の案内や必要書類の準備をサポートしてもらえます。確実に合意内容を履行させる保障として、公正証書化は非常に有効です。
専門家(行政書士等)に依頼する利点
離婚協議書の作成や公正証書化の手続きは、法律の専門知識が要求されるため、行政書士など専門家に依頼するのが確実です。専門家に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
条項漏れやミスの防止
当事者だけで協議書を作成すると、法的に重要な項目を見落としたり不明確な表現になったりしがちです。行政書士に依頼すれば、財産分与や年金分割の細かな取り決め、清算条項(将来一切請求しない旨)など必要事項を盛り込んだ適切な書式の協議書を作成できます。
迅速かつ確実な手続き
公正証書を作成する場合、事前準備や公証人とのやり取りに手間がかかりますが、行政書士に依頼すればスケジュール調整や必要書類の準備などの手続きを代行・サポートしてもらえます。忙しい時でもプロに任せれば安心です。
精神的負担の軽減
長年連れ添った相手との交渉は心身ともに負担が大きいものです。第三者である専門家が間に入ることで冷静な協議が進みやすくなり、当事者の心的ストレスも軽減されます。(弁護士法に反する交渉や仲裁等はできません。)
行政書士として、依頼者の方が適切な離婚協議書や離婚公正証書を整えることで、離婚後の権利を守り、安心して新生活を迎えられるよう全力でサポートいたします。専門家の力も借りながら、確実な合意形成と手続きを進めていきましょう。
離婚後に必要な手続き
離婚が成立した後も、各種の手続きや届け出を速やかに行う必要があります。熟年離婚では長年使い慣れた姓や生活環境が変わるため、忘れずに対応しましょう。ここでは、離婚後に行うべき主な手続きとして、離婚届・戸籍の手続き、社会保険や年金の変更手続き、そして財産分与や年金分割の実行に分けて説明します。
離婚届の提出と氏・戸籍の変更
夫婦双方で離婚内容に合意したら、役所に離婚届を提出します。離婚届には成人2名の証人署名が必要なため、事前に用意しておきましょう。協議離婚の離婚届が受理されると離婚が成立します。
離婚後の姓(氏)については、原則として結婚前の旧姓に戻る(復氏)ことになりますが、婚姻時の姓をそのまま名乗りたい場合は離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります(届出をしないと自動的に旧姓に戻ります)。
姓が変わる場合、自分の戸籍も新たに編製される(新戸籍を編製する)ことになります。離婚成立後速やかに、運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、クレジットカードなど各種証明書や契約の氏名変更手続きを行いましょう。
年金・健康保険の切替え手続き
離婚後は、社会保険の種別変更や年金分割の実施手続きを速やかに行います。まず、専業主婦で夫の扶養に入っていた方(第3号被保険者)は、第1号被保険者(自営業・無職等)への種別変更届を年金事務所に提出します。
これにより、自身で国民年金保険料を納付し続けることになります(経済状況に応じて免除申請も検討)。次に、離婚時年金分割の請求手続きを行います。離婚後2年以内(法改正により5年以内、ただし令和7年6月時点では未施行。)に夫婦双方または片方から年金事務所へ請求しなければ、年金分割ができなくなるため注意してください。
離婚協議書や公正証書に定めた按分割合に従い、厚生年金の分割手続きを完了させます。健康保険についても、夫の被扶養者から外れるため、自身で国民健康保険に加入するか、新たな勤務先の健康保険に加入する手続きを行います(離婚後14日以内)。国民健康保険への加入は市区町村役場で行いますが、離婚に伴う加入であれば年金機構から資格喪失連絡が行くため、離婚日からの期間について保険料が遡って請求されることになります。あわせて、離婚により住民票の住所変更が必要な場合は転居届も提出しましょう。
財産分与・精算事項の実行とその他の届出
離婚成立後は、合意した財産分与や金銭の支払い等を確実に履行します。慰謝料や財産分与金の一括支払いがある場合は指定口座への振込確認を行い、分割払いの場合はきちんと期日どおり支払われているか管理します。
公正証書を作成していれば、滞納時には速やかに強制執行の手続きを検討しましょう。住宅の名義変更や財産の分配(例えば自動車の所有者変更や不動産の登記変更など)も速やかに行います。特に不動産の登記変更が必要な場合、司法書士など専門家に依頼すると安心です。
その他、離婚後に行う届出として、公的年金以外の年金制度(企業年金や厚生年金基金からの脱退手続き)、各種保険の受取人変更(生命保険の受取人が元夫のままになっていれば変更)、携帯電話や公共料金の契約名義変更なども必要に応じて対応します。氏名や住所の変更が伴うため、一つ一つ手続きを進めていきましょう。
熟年離婚は人生の大きな転機ですが、以上のような準備と手続きを着実に進めれば、新しい生活への船出もスムーズに切ることができます。不安な点は専門家に相談しながら、一つひとつやるべきことをクリアしていきましょう。それが、後悔のない円満な熟年離婚と、離婚後の安心した暮らしにつながります。
熟年離婚のやることリスト【まとめ】
- 離婚後の生活費をシミュレーションし、必要な収入額を把握する
離婚後、自分一人で生活していくために毎月どれだけの生活費が必要かを、家計簿や通帳の履歴をもとに試算します。
- 夫婦の共有財産・負債をリストアップし、証拠資料を確保する
預貯金、不動産、保険、株式、自動車、家具・貴金属、退職金見込額など、結婚期間中に築いた財産を洗い出します。
- 離婚後の仕事・住まいの見通しを立て、就業や住居確保の準備を進める
離婚後の自立に向けて、仕事を見つけて収入源を確保しておくことが大切です。
- 財産分与・年金分割・慰謝料・養育費など、離婚協議で決めるべき条件を整理する
離婚時には金銭面の取り決めが重要です。
- 年金や保険制度、保障の見直しと整理を行う
年金分割によってどの程度の受給額となるか、企業年金・共済年金の取扱いや健康保険の切り替えなども併せて検討します。
- 離婚協議書を作成し、必要に応じて公正証書として整備する
離婚協議で合意した内容は、必ず書面(離婚協議書)にまとめ、双方が署名・押印して保管します。
- 離婚届を提出し、姓や戸籍・氏名に関する変更手続きを行う
協議離婚が成立したら、役所に離婚届を提出します。証人2名の署名が必要なため、事前に準備しておきます。
- 年金・健康保険など社会保険関係の切替え手続きを行う
専業主婦で夫の扶養に入っていた場合は、第3号被保険者から第1号へ種別変更が必要です。
- 財産分与・慰謝料等の履行状況を確認し、未払い時には強制執行を検討する
財産分与金や慰謝料の支払いがきちんと行われているかを継続的に確認します。
熟年離婚に関する各種サポートは、当事務所にお任せください
![]()
熟年離婚は、人生の大きな節目となる重要な手続きです。行政書士として、当事務所では次のようなお悩みをお持ちの方を丁寧にサポートいたします。
特に次のようなお悩みをお持ちの方はご相談ください。
- 離婚後の生活設計に不安があるため、金銭計画や受け取れる財産を具体的に整理したい
- 年金分割や財産分与について何をどう取り決めるべきか分からない
- 離婚協議書を自分で作るのが難しく、法的に通用する形で書面化したい
- 慰謝料や財産分与の不履行に備えて、公正証書を作成したい
- 離婚後の社会保険・年金・保険の変更手続きを一つずつ教えてほしい
- 離婚を切り出す前に準備しておくべきことを、専門家と一緒に整理したい
当事務所では、離婚協議書の作成から公正証書手続、公証役場同行、年金分割情報通知書の取得支援、氏名変更・保険手続きのご案内までサポートを行っております。(なお、公正証書手続以降はご要望があった場合です。)安心して新しい生活を始めるために、まずは一歩踏み出してご相談ください。
サービスの特徴
きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。
離婚協議書作成の流れ
- 初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。 - 契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。 - 協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。 - 協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。 - 協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| ⑴離婚協議書の作成と製本 | 44,000円 | 離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。 |
| ⑵離婚公正証書の作成サポート (上記⑴を含みます。) | 77,000円~ | 離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。 |
※)上記金額に実費がかかります。
当事務所にお任せいただくメリット
- 安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。 - 時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。 - トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。 - 専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。
お問い合わせ
離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
お客様の声
お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。
![]()
【政府の記事】
日本年金機構「離婚時の年金分割」
法務省「年金分割」
法務省「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」
厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」
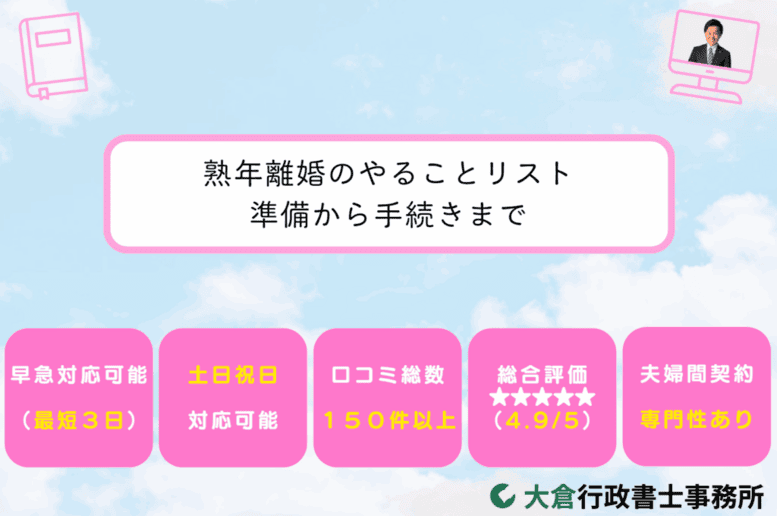



コメント