2024年5月、父母が離婚した後も共同で親権を持つことを可能にする民法改正法が成立しました。この改正により、従来は離婚時に父母のいずれか一方しか持てなかった親権(単独親権)を、夫婦の話し合いで双方が持つ共同親権にすることも選択できるようになります。
施行は一部例外を除き2026年5月までに予定されており、近い将来、離婚後の子どもの養育環境が大きく変わる見込みです。離婚を考えている夫婦にとって、この法改正のポイントや離婚協議で決めておくべき事項を正確に理解し、適切に準備することが大切です。
本記事では行政書士の視点から、共同親権への民法改正に焦点を当て、改正民法の内容や離婚協議書・公正証書の作成ポイント、家庭裁判所の判断基準、日常生活における親権行使の範囲、実務上の注意点などを専門的かつ網羅的に解説します。
離婚後も子どもの利益を第一に、父母が協力して子育てできるようになる新制度について、一緒に確認していきましょう。
民法改正で実現した共同親権制度の概要とポイント
![]()
本トピックでは、2024年成立の民法改正で導入される離婚後の共同親権制度の概要と主なポイントを解説します。
まずは従来の日本の単独親権制度とその問題点を整理し、今回の改正によって何が変わるのかを押さえましょう。
さらに、協議離婚や裁判離婚における親権者決定の方法と、家庭裁判所が共同親権と単独親権を判断する基準(子の利益を最優先する原則やDV等の場合の取扱い)について説明します。共同親権導入の背景にある子どもの利益確保の考え方も踏まえ、新制度の全体像を把握しましょう。
従来の単独親権制度とその課題
日本の現行民法(改正前)では、子どもが未成年の場合、離婚後の親権者は父母のどちらか一方のみと定められていました。
婚姻中は父母が共同で親権を行使しますが、離婚すると法律上は一人だけが親権者(単独親権者)となり、原則としてその親だけが子どもの監護・教育や財産管理など子どもに関する重要事項の決定権を持つことになります。
もう一方の親(非親権者)は法律上これらの権限を失い、子どもの養育に直接関与できる範囲が限定されていました。例外的に「親権者とは別に監護権者を指定する」ケース(つまり法律上は片方が親権者だが、実際の子の世話は他方が担う取り決め)もありましたが、一般的ではありません。
この単独親権制度には様々な課題が指摘されてきました。例えば、離婚後に「本当は両親で協力して子育てしたい」と望んでも法的には片親しか親権を持てず、もう片方の親は意思決定に関われないため、子育てへの継続的な関与が難しくなります。
また、子どもの成長に両親の関与が重要と分かっていても、一方の親との関係が断絶・希薄になりやすい傾向がありました。さらに養育費の未払い・面会交流拒否などの問題も、単独親権制度下では「親権者でない側」の親の子育て当事者意識が希薄になりがちなことが一因と考えられています。
2024年民法改正による共同親権導入の内容
こうした課題を受け、2024年に成立した改正民法では離婚後の親権制度が大きく見直されました。最大のポイントは、離婚後の親権について父母が「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになったことです。
具体的には、協議離婚(話し合いによる離婚)の場合には夫婦の協議により「父母双方を親権者とする(共同親権)」か「どちらか一方を親権者とする(単独親権)」かを定めることが可能になります。離婚届に双方または一方を親権者として記載する形で、共同親権を選ぶこともできるわけです。
一方、裁判所の関与する離婚(調停離婚や裁判離婚)の場合には、家庭裁判所が父母双方または一方を親権者と定めます。改正法により、裁判所も共同親権か単独親権かを指定できるようになりました。
ただし、後述するように裁判所が共同か単独かを判断する際は子の利益(子どもの福祉)を最優先に考慮することが法律上明記されています。
また今回の改正では、親権に関する規定以外にも、子の養育に関する父母の責務の明確化、養育費支払い確保の仕組み強化(いわゆる「法定養育費」の創設等)、安全な親子交流の実現に向けた規律(別居親の両親や兄弟との交流容認など)の見直し、離婚後の養子縁組手続の見直し、財産分与請求期限の延長(離婚後2年→5年)等、関連する家族法制度全般に幅広い改正が行われています。
【関連記事】
>【民法改正】離婚協議書で養育費の強制執行が可能って本当?
共同親権か単独親権かを決める方法と家庭裁判所の判断基準
協議離婚の場合、親権者は基本的に夫婦の話し合いによって決定されます。改正後の民法819条1項は「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。」と規定し、当事者の協議で共同親権または単独親権のいずれかを選べることを明文化しました。
したがって離婚届提出までに、夫婦間でどちらの形にするか合意しておく必要があります。なお、新法では例外的な手続も設けられ、協議離婚時に親権者を定められない場合でも、家庭裁判所の調停(審判)を申し立てれば、一旦親権者未定のまま離婚を成立させることも可能になります。この場合、後日家庭裁判所で親権者を決めてもらうことになります。
家庭裁判所が親権者を指定する際の判断基準は下記のとおり大きく二段階に分かれます
共同親権とすると子の利益を害する恐れがある場合
この場合は必ず単独親権としなければならないとされています。具体例として法律の付則では下記2つが挙げられています。
- 共同親権とすれば子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合
- 父母が共同して親権を行うことが困難な事情(DV等)がある場合
たとえば一方の親から子への虐待や深刻な心理的悪影響の恐れがあるケース、あるいは配偶者暴力(DV)等で父母間の協力が不可能なケースでは、共同親権は子の福祉を損なうため選択できません。このような場合、裁判所は共同親権を認めず一方の単独親権とすることが義務付けられます。
上記以外の場合
共同親権が直ちに子の利益を害する事情がない場合は、子の利益(子どもの最善の利益)の観点から総合的に判断して共同親権か単独親権かを決定します。
つまり「共同親権が原則」「単独親権が原則」といった一律の優先ルールがあるわけではなく、あくまで子どもの幸せや安定を最優先に、親子関係や父母間の関係、これまでの養育状況、今後の生活環境その他一切の事情を考慮して最適な形を裁判所が判断します。
共同親権だから有利・単独親権だから有利という先入観は持たず、子どもにとって何がベストかを基準に決められるわけです。
このように、協議離婚では夫婦の協議次第で共同親権を選択できますが、調停・裁判では子の利益を害する恐れがある場合は共同親権が認められず、それ以外でも最終的には子どもの幸せを軸に共同か単独か判断されます。
したがって、DVや虐待があるケースでは迷わず単独親権が選択される一方、そうでない場合でも両親の対立が激しく子の福祉が損なわれる恐れが強いと判断されれば単独親権になり得ますし、逆に両親が協調して子育てでき子に良い影響が期待できる環境なら共同親権が適切と判断されるでしょう。
家庭裁判所は個別事情を丁寧に考慮しますので、仮に裁判になった場合には夫婦それぞれが「なぜ共同(または単独)が子にとってベストなのか」を具体的に主張・立証していく必要があります。
共同親権を選択する際の離婚協議書作成のポイント
![]()
本トピックでは、協議離婚に際して共同親権を選択する場合に夫婦が合意しておくべき事項と、その内容をまとめる離婚協議書・公正証書の作成ポイントを解説します。離婚後の子どもの養育で揉めごとが起きないよう、事前にしっかり話し合い、書面に残すことが重要です。
親権の指定(共同か単独か)はもちろん、養育費や面会交流などの取り決めも含め、離婚協議書に盛り込むべき項目を確認しましょう。
また、共同親権の場合に検討すべき親権者・監護者の指定や養育計画についても触れ、実務上の注意点を紹介します。行政書士として、正確で抜け漏れのない合意内容の文書化のポイントをお伝えします。
協議離婚で決めておくべきこと:子どもの養育に関する合意事項
離婚を協議で行う場合、夫婦間であらかじめ取り決めておくべき事項がいくつかあります。特に未成年の子どもがいる場合、以下のようなポイントについて明確に合意しておくことが重要です。
親権者の指定
まずは離婚後の親権をどうするか決めます。改正民法施行後は共同親権とするか単独親権とするかを選択できますので、夫婦で十分話し合いましょう。共同親権を選ぶ場合も離婚届にその旨を記載する必要があります。
なお共同親権とした場合でも、後述するように日常的な子育ての主体や子どもの居住先を誰にするか等について取り決めておくことが望ましいです。
監護者・子の居所
共同親権の場合でも、子どもが実際にどちらの親と暮らすか(主たる監護者)を指定することが可能です。これについては後述しますが、協議離婚の段階で「子どもは○○(父または母)と同居させ、もう一方の親は定期的に面会する」等、子の生活拠点と面倒を見る主体を話し合っておくと良いでしょう。
単独親権の場合も、親権者となる側がそのまま子どもを引き取り養育するケースが多いですが、もし例外的に「法律上の親権者」と「実際に子を育てる監護者」を分ける場合はその旨取り決めが必要です。
一般には親権者=監護者とするのが自然ですので、特別な事情がなければ親権者となる方が子を養育する形になります。
養育費の取決め
養育費とは子どもを引き取らない側の親が支払う子育て費用の分担金です。子ども一人当たりの月額金額、支払方法(口座振込等)、支払日や支払期間(一般に子が成年に達するまでなど)を具体的に決めます。
養育費の金額は夫婦の収入や子の年齢・人数に応じ、家庭裁判所の算定表を参考に決定するケースが多いです。また将来の金額見直し条件(例えば進学時に増額検討など)や物価変動への対応も話し合っておくと良いでしょう。
面会交流(親子交流)の方法
子どもと別居することになる親と子が定期的に会ったり交流したりする面会交流についても、具体的な取り決めを行います。
たとえば「月1回第二日曜日に面会」「夏休みと冬休みに各○日間宿泊を伴う面会を許容」など頻度・日時・場所を定めます。あわせて、受け渡し方法(学校で引き渡すか、自宅訪問か、中間地点で引き渡すか等)や連絡手段、面会時に祖父母等第三者の同伴を認めるかなど細かいルールも決めておくと後々トラブルを防げます。
共同親権を選択した場合、法的に双方が親権者となるため、一方の親が他方による面会を一方的に拒むことは従来より難しくなると考えられます。子どもの福祉のためにも、別居親との適切な交流方法を合意しておくことが大切です。
その他の取り決め
上記以外にも、慰謝料(離婚原因を作った配偶者が支払う精神的苦痛への賠償金)の有無・金額・支払方法、財産分与(婚姻中に築いた財産の分配方法、持ち家や車などの名義変更や処分方法)など、離婚条件全般について夫婦間で合意します。
未成年の子がいる場合は主に親権・監護や養育費・交流が中心となりますが、離婚に伴う経済的条件や手続事項も含め包括的に協議しておく必要があります。
以上のような事項について夫婦間で明確に合意できたら、その内容を口約束で終わらせず書面に残すことが非常に重要です。次の節では、それを形にする離婚協議書や公正証書について説明します。
親権者・監護者の指定と養育計画のポイント
共同親権を選択した場合、離婚協議書には親権者として「父母双方」と記載されることになります。しかし、それだけでは実際の子育ての役割分担が不明確な場合があります。そこで検討したいのが「監護者」の指定と養育計画の作成です。
監護者の指定について
改正法では、共同親権の場合でも親権者とは別に「子の監護者」を指定できることが明確化されました。監護者とは、「子どもと一緒に暮らし、日常的な世話や教育を担当する親」のことです。
例えば「共同親権者:父母両名、監護者:母」と指定すれば、法律上は父母が共同で親権を持ちつつ、子どもの普段の生活や養育は母が中心となって行うことが明確になります。
監護者を定めることで子どもの生活基盤が安定し、日常の細かなことまでいちいち両親の協議が必要になる事態を避けられます。
養育計画(親子の生活プラン)の策定
共同親権の場合は特に、離婚後に子どもをどう育てていくかについて具体的なプランを夫婦で共有しておくことが重要です。養育計画とは、離婚後の子育ての方針や取り決めを詳細に書面化したものです。
法律上提出義務があるものではありませんが、例えば「日常の送り迎えや習い事の対応は主にどちらが行うか」「進学や医療の大きな判断をどう協議するか」「連絡や情報共有の方法(連絡帳や専用アプリを使う等)」といった事項をあらかじめ話し合って文書にまとめておけば、共同で親権を行使する際の指針となります。
家庭裁判所でも調停の場などで養育計画書の提出を促すことがありますし、何より両親の認識違いによるトラブルを防ぐ効果があります。当事務所を含め行政書士に相談すれば、チェックリストに沿って抜け漏れのない養育計画を作成するサポートを受けることもできます。
【関連記事】
>養育計画書の書き方とテンプレート
親権行使に関する特約
共同親権を円滑に機能させるため、離婚協議書や公正証書にいくつか特約事項を定めるケースも考えられます。例えば「緊急時を除き、子に重大な影響を及ぼす事項(進学先、手術同意等)は必ず事前にもう一方と協議する」「協議が整わない場合は家庭裁判所の調停を利用する」といった取り決めを書いておくことも可能です。
もっとも、法律上もともと重大事項は共同決定が原則ですから、改めて書かずとも同じ意味にはなります。しかし文書で約束しておくことで双方の意識が高まり、トラブル予防に繋がるでしょう。
このように、共同親権を選ぶ際には監護者を指定するか検討し、子どもの養育に関する具体的なプランやルールを合意しておくことが大切です。決めた内容は離婚協議書に盛り込み、必要に応じて公正証書化することで、離婚後の共同養育をスムーズにスタートできるでしょう。
共同親権でも一方が単独でできる日常行為とは
![]()
共同親権になれば、基本的には子どもの重要な事項は父母が共同で決定することになります。しかし、日常生活の細かな場面まで全て両親の同意が必要では現実的ではありません。そこで改正民法では、共同親権の場合でも一方の親が単独で親権を行使できるケースを明示しています。
それが「日常の監護・教育に関する行為」および「子の利益のために急迫の事情があるとき」等の場合です。本トピックでは、共同親権時における単独判断可能な日常行為の具体例と、その範囲について説明します。
また併せて、原則的に両親の合意が必要となる重要事項にはどんなものがあるのかにも触れます。共同親権といえども、日々の子育ての現場で迅速に判断できる仕組みが用意されていることを理解しましょう。
日常の監護および教育に関する行為は単独で可能
改正後の法律では、たとえ親権者が共同であっても、「子の監護及び教育に関する日常の行為」については各親が単独で親権を行使できると定められました。
これは日々の子育てに関する細かな判断まで逐一もう一方の親の同意を求める必要はないという意味です。典型的な日常行為の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 子どもの毎日の食事内容や栄養管理
- 季節や成長に応じた衣服の選択(どんな服を着せるか)
- 生活必需品やおもちゃなど子どものための日常的な買い物
- 学校・保育園への送り迎えや連絡帳への対応、学校行事への参加
- 週末の習い事やクラブ活動への参加判断
- 定期的な予防接種や軽い風邪の通院など、子の心身に重大な影響を及ぼさない範囲の医療行為の同意
- 短期間の旅行(数日程度の観光旅行や帰省など)
- 高校生以降であればアルバイトの許可など
上記のような日常的事項は、子どもと一緒に暮らしている親がその場で判断しなければならない場面が多く、逐一もう一方の親に連絡して許可をもらうのは現実的ではありません。
そこで法律上も日常生活に関する行為であれば共同親権であっても各自が単独で決めて良いとされています。
例えば、今日の夕飯に何を食べさせるかや、子どもにどんな服を着せるかといったことにいちいち両親の合意書面が必要では困りますから、当然と言えば当然の規定でしょう。
もっとも、「日常行為」に当たるか否かの線引きが難しいケースも考えられます。一見日常の延長のようでも、子どもの将来に影響を与えうる事項は単独判断できるか微妙です。
例えば塾や習い事の選択は日常的な教育行為とも言えますが、その費用負担や進路への影響によっては重要事項と捉えられる可能性もあります。法律上は明確に区別されていなくとも、高額な出費を伴う習い事や長期間に及ぶ活動への参加などは、できれば事前にもう一人の親と話し合って決める方が無難です。
日常行為だからと独断で物事を進め、それが子の将来に大きく影響する結果となった場合、後で相手方から異議が出てトラブルになる恐れもあります。
子の利益のため急迫の事情がある場合の単独対応
共同親権下でもう一つ、例外的に一方の親が単独で即時に対応できる場合として定められているのが「子の利益のため急迫の事情があるとき」です。これは子どもの身に差し迫った危機や期限の迫った重要事が発生した場合、いちいち相手の同意を待っていられないケースを想定しています。具体的な例として、以下のような事態が考えられます。
- 子どもが事故や急病で緊急の手術が必要な場合(生死に関わるような緊急医療措置)
- 希望する学校への入学手続の期限が目前に迫っている場合(もう一方と連絡が取れなくても期限内に手続きを済ませなければならない)
- 別居親によるDV・児童虐待などから子どもを避難させる必要がある場合(安全確保のため子を一時的に転居させる等)
このような「急迫の事情」があるときは、共同親権者の一人が単独で子どもの治療に同意したり、安全な場所へ避難させたりする権限が認められます。
子どもの命や健康を守るための緊急措置について、もう片方の親の許諾を得られないからと何もしないのでは本末転倒だからです。当然ながら、こうした緊急時に事後報告で問題ない範囲とはいえ、発生後には速やかにもう一方へ状況を伝え、必要に応じて事後承諾を得るのが望ましいでしょう。
ただし、何が「急迫の事情」に該当するかは場合によります。法律上明文化された例としては上記のようなケースですが、例えば子どもが親の了承なく高額な契約を結ぼうとしているのを止めるといった場合も急迫性があるかもしれません。
この点、取引の相手方からすると「本当に急迫性があるのか」「これは日常行為と言えるのか」判断がつかず不安になり、結局念のためもう一人の親の同意を求めてくる可能性はあります。つまり法律で単独行使が認められていても、実務的には「本当にそれだけで大丈夫か?」と第三者が慎重になることも想定されます。
以上のように、共同親権でも様々な例外場面で片親による迅速な意思決定が許容されますが、それ以外の重要事項については従来通り父母双方の合意が必要である点に注意が必要です。
繰り返しになりますが、共同親権とは両親が子の重要事項を共同で決めていく制度です。日常的なことや緊急時には各親の機動的対応を認めつつ、それ以外の大切な判断は必ず二人で話し合うという原則を忘れないようにしましょう。
共同親権選択のメリット・デメリットと実務上の注意点
![]()
最後に、離婚後の共同親権制度を実際に利用する上で知っておきたいメリット・デメリットや、共同親権を選ぶ際の実務的な注意点について解説します。共同親権には、離婚時の親権争いを回避し子どもに両親の愛情と関与を確保できるといった利点が期待される一方で、父母間の協議が難航すると子どもの意思決定が滞るリスクなど課題も指摘されています。
ここでは共同親権の長所短所を整理し、さらに家庭裁判所の役割や既に離婚している場合への影響、円滑に共同養育するためのポイントなど実践的な視点から説明します。
共同親権のメリット・期待される効果
改正により共同親権が選択肢に加わることで、従来の単独親権制度にはない以下のようなメリットが期待されています。
親権者をめぐる争いを防ぎやすい
離婚時に「どちらが親権を取るか」で激しく争うケースがありますが、共同親権という選択肢があれば両方が親権者になるため、ゼロサムの争奪戦を避けやすくなります。夫婦間の話し合いが比較的穏便にまとまりやすく、子どもを巡る紛争の長期化を防ぐ効果が期待できます。
離婚後も協力して子育てが可能
共同親権であれば、離婚後も父母が共に法的な保護者として責任を共有します。お互い親権者という立場が子どものため協力する動機付けとなり、教育方針や子どものケアについて相談・協調しやすくなります。
両親が役割分担しつつ協力して養育に関われるため、シングルでは難しい手厚いサポートを子どもに提供できる可能性があります。
養育費不払いの抑止
日本では離婚後の養育費不払いが大きな社会問題ですが、共同親権になれば非同居親も「自分も子育てに責任を負っている」という意識を持ちやすく、養育費支払いへのモチベーション向上が期待できます。
実際、母子家庭の半数以上・父子家庭の8割近くで養育費の取り決めすらなく、支払い受領率も母子家庭で28.1%に過ぎない現状があります。共同親権によって心理的責任感が増せば、養育費の取り決め・履行率向上につながるとの見方があります。
面会交流の円滑化
単独親権下では、親権者ではない親が子どもに会うには親権者の許可が必要なため、離婚後に面会交流が途絶える例も少なくありません。共同親権であれば両者が対等な親権者なので、一方の判断だけで他方との面会を拒むことは難しくなります。
結果として子どもが離婚後も両親それぞれと定期的に交流しやすくなり、子にとって安定した親子関係を維持できるメリットがあります。
子どもの心理的安心感
形式上とはいえ離婚後も「お父さんもお母さんも自分の親権者なんだ」と子どもが理解できれば、離婚による喪失感や不安が和らぐ可能性があります。両親から見放されたと感じにくくなり、子どもの精神面への好影響も期待されています。
以上のように、共同親権は子どもに両親の愛情と関与を両立させる制度として歓迎する声があります。親同士も「どちらかが親権を失う」形にならないため、離婚後の関係性が比較的良好に保てるという利点も指摘されています。
共同親権のデメリット・留意すべき課題
一方で、共同親権には以下のようなデメリットや懸念点もあります。
- 意思決定に時間がかかる可能性
何か子どもに関する重要な決定をする際、共同親権だと常にもう一方と協議して合意を得る必要があります。両親の意見が割れた場合、結論が出るまで子どもの進路や治療方針が決められず宙に浮く恐れがあります。単独親権なら親権者の判断で即決できたことが、共同親権では長引くケースがある点に注意が必要です。
- 新たな争いの火種になり得る
離婚時に親権争いを避けられても、離婚後に子どものことで再び衝突するリスクがあります。例えば進学先や習い事をめぐって意見が対立し、調停や裁判に発展するケースも考えられます。
共同親権だから必ずしも平和というわけではなく、むしろ離婚後もずっと意思疎通と合意形成が求められるため、関係が悪化すればトラブルが長期化する可能性があります。
- DV・モラハラから逃れにくい
配偶者からのDV(家庭内暴力)やモラハラに悩んで離婚した場合、共同親権だと離婚後も加害的な元配偶者と関わり続けなければならない状況になりかねません。
相手が子どものことを口実に接触してきたり、子どもをコントロール下に置こうとする懸念もあります。改正法でもDV等がある場合は共同親権にしないとされていますが、離婚後に問題が顕在化するケースもあるため慎重な判断が必要です。
- 子どもの負担増加
両親が仲睦まじく協力できれば良いのですが、現実には離婚に至る夫婦は何らかの不和があります。共同親権の名の下で両親が頻繁に対立すると、その板挟みになる子どもに心理的負担がかかります。
また二つの家庭を行き来する生活パターン(例えば週末ごとに行き来等)になれば、環境変化への適応や荷物移動など子ども自身の負担も増えます。
- 居住地や再婚の自由に制約
共同親権の場合、片方が遠方へ引っ越すことは子の監護に重大な影響を及ぼすため容易ではありません。転居や子連れの海外移住などは共同親権者双方の合意事項となるため、一人の判断で動けない不自由さがあります。
また一方が再婚して新たな家庭を築く場合にも、子どもの親権問題が絡むことで調整事項が増えるでしょう。単独親権であれば親権者の再婚に際し相手の同意は不要ですが、共同親権だと配偶者と子の関係について事前協議が望ましい場合も出てきます。
以上のように、共同親権には両親の高い協調精神とコミュニケーション力が求められ、そうでなければかえって子どもに悪影響が及ぶ恐れがあります。制度の趣旨は子の利益重視ですが、現実に父母関係が険悪であれば共同親権は適しません。
このため裁判所も、DV・虐待など共同養育困難な場合は共同親権を認めないルールとしています。
円滑に共同養育を行うための実務上のポイント
最後に、共同親権を選択する夫婦が円滑に共同養育していくための実務的ポイントをまとめます。
- 離婚前の十分な話し合いと取り決め
共同親権を選ぶのであれば、離婚前にできるだけ細かなことまで協議し、合意事項を離婚協議書等に明記しておきましょう。トラブルの芽は事前に摘んでおくのが肝心です。特に先述の養育計画をしっかり作成することで、離婚後の役割分担が明確になりスムーズなスタートが切れます。
- 子の利益最優先の姿勢
何より大切なのは、常に子どもの幸せと健全な成長を第一に考える姿勢です。意見の相違が出ても、自分の感情や利害ではなく「この決定は子にとってベストか?」を基準に歩み寄るよう心掛けましょう。子どもの前で相手の悪口を言ったり争ったりするのは厳禁です。
- 定期的なコミュニケーション
共同親権では離婚後も一定のコミュニケーションが不可欠です。連絡手段や頻度を決め、子どもの様子や学校からの連絡事項などを共有しましょう。例えば月に一度は面談またはオンラインで子の近況を話し合う場を設ける、連絡ノートや専用のアプリを活用するといった方法があります。情報共有と意思疎通を怠ると不信感が募りやすいので注意してください。
- 第三者の力を活用
どうしても意見が合わないとき、無理に二人だけで解決しようとせず第三者のサポートを利用しましょう。離婚後の養育に関する調停手続は家庭裁判所で利用できますし、各地のファミリー調停センターや民間の養育コーディネーターを頼ることもできます。
離婚時の書類作成等のサポートはお任せください
![]()
当事務所では、離婚に伴う書類作成を専門業務の1つに扱っております。これまでに協議書としての作成をはじめ、公正証書の作成サポートなども数多くかかわってきました。
書類の作成業務は全国対応が可能ですので、是非一度ご相談ください。
サービスの特徴
きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
全国対応
当事務所は奈良県生駒市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については大阪府、兵庫県などの近畿圏を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。
離婚協議書作成の流れ
- 初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。 - 契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。 - 協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。 - 協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。 - 協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。
料金
| サービス | 料金(税込) | 概要 |
|---|---|---|
| ⑴離婚協議書の作成と製本 | 44,000円~ | 離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。 ご希望に応じて公正証書への移行サポートも可能です。 |
| ⑵離婚公正証書の作成サポート (上記⑴を含みます。) | 77,000円~ | 離婚公正証書の原案作成をサポートさせていただきます。 代理調印の有無などにより費用が異なります。 |
※上記金額に別途、実費(郵送料・公証人手数料等)がかかります。
当事務所にお任せいただくメリット
- 安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。 - 時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。 - トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。 - 専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。
お問い合わせ
離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
お客様の声
お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。
![]()
【政府の記事】
法務省「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」
厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」


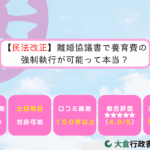

コメント