長年連れ添った夫から突然「離婚したい」と言われたら、驚きと戸惑いで頭が真っ白になることでしょう。突然の申し出に動揺するのは当然ですが、将来の生活を守るためには冷静な対処が求められます。熟年離婚というと妻から切り出すイメージが強いですが、近年では男性から離婚を求めるケースも増えています。
ある調査では、熟年離婚の約4割が夫から切り出されているという報告もあります。「どうして今更…?」と感じるかもしれません。しかし、夫から熟年離婚を切り出された場合でも、落ち着いて対応し適切な準備をすれば、将来の不安を軽減し納得のいく結果を得ることができます。
本記事では、夫から離婚を求められた妻が取るべき対応策や心構え、そして離婚に際して準備しておくべきことについて、行政書士の視点から詳しく解説いたします。熟年離婚に直面している方が安心して一歩を踏み出せるよう、法的観点と実務的アドバイスを交えてお伝えします。
離婚を受け入れるべきか迷ったとき
![]()
夫から熟年離婚を切り出されたとき、まず頭をよぎるのは「本当に離婚に応じるべきなのか?」という迷いでしょう。長年築いてきた家庭や思い出を考えると、簡単に「はい」と答えられないのが当然です。夫婦の今後を左右する重大な決断だけに、軽々しく結論を出せないのも無理はありません。
このトピックでは、離婚に同意すべきか迷う妻のために、考慮すべきポイントを解説します。
法律上、一方的な離婚はできない
日本の法律では、双方が合意しない限り離婚届を提出することはできません。夫から離婚を求められても、あなたが納得できない場合、すぐに応じる必要はありません。相手の一存で離婚が成立することはないので、まずは心を落ち着けましょう。
ただし、だからといって何年も話し合いを先延ばしにすれば解決するわけではなく、問題の根本に向き合う必要があります。なお、夫が勝手に離婚届を提出してしまうリスクに備え、市区町村役場に「不受理申出(※1)」を出しておくことも検討できます。万一合意のない離婚届が提出されても受理されなくなるための手続きです。
(※1)不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされても、自ら窓口に出頭して届出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出るものです。不受理申出は、申出人が取下げしない限り有効です。(参考 「大阪市 不受理届出」)
離婚の理由と気持ちを確認する
夫がなぜ離婚を望んでいるのか、その背景を冷静に探ってみましょう。長年のすれ違いや夫婦間の不満が原因であれば、改善の余地があるかもしれません。お互いに本音で話し合うことで、誤解が解けたり修復の道が見える可能性もあります。
すぐに離婚という結論を出す前に、夫婦関係を見直し、修復できる部分はないかを検討してみる価値があります。場合によっては夫婦問題に詳しいカウンセラーなど第三者の力を借りて、関係改善に努めることも選択肢の一つです。
離婚を拒否し続けるリスクも知る
一方で、あなたがどうしても離婚に応じたくない場合、法的には拒否し続けることも可能です。しかし夫が強く離婚を望めば、家庭裁判所での調停や裁判に発展する可能性があります。
特に夫側に明確な離婚理由(不貞やDVなど)がない場合、裁判所もすぐに離婚を認めないことがありますが、別居が長引けばいずれ認められるケースもあります。一般的には、別居期間が5年前後続くと夫婦関係が完全に破綻したと判断され、離婚が認められやすくなると言われています。
安易に離婚に同意する必要はありませんが、単に拒み続けるだけでは事態が悪化する恐れもあるため、慎重な対応が求められます。
夫から離婚を切り出されたときの具体的な対応
![]()
夫から離婚の申し出を受けた際には、感情的にならず冷静に対応することが大切です。焦って結論を出すのではなく、自分の今後の生活を守るためにも適切なステップを踏みましょう。このトピックでは、離婚を切り出された直後から取るべき具体的な対応策を説明します。
気持ちが揺れる中でも、自分の権利と生活基盤を守るために、どのような行動を取るべきか整理しておきましょう。
情報収集と専門家への相談
まず、自分の権利や今後の生活設計について情報収集しましょう。離婚後の生活費や年金、財産分与の割合など、知っておくべきことは多岐にわたります。不安であれば早めに専門家に相談することをおすすめします。
離婚業務を扱う行政書士などの専門家に相談すれば、離婚協議の進め方や取り決めるべき事項についてアドバイスを受けられます。自治体の女性相談センター(大阪府の場合)など、公的な支援機関を頼るのも有効です。
第三者の意見を聞くことで、感情的になりがちな状況でも冷静な判断材料を得ることができます。また、信頼できる友人や家族に気持ちを打ち明け、精神的なサポートを得ることも心の安定につながります。
条件面の交渉を行う
離婚に応じる場合でも、あなたの生活を守るための条件交渉はしっかり行いましょう。長年連れ添った夫婦であれば、共有の財産や年金、退職金などの金銭面の清算が必要です。
財産分与と持ち家の取り扱い
婚姻期間中に築いた財産(預貯金、不動産、株式など)は、原則として夫婦で半分ずつに分ける「財産分与」の対象となります。特に持ち家がある場合は、その扱いを明確にする必要があります。
- 売却して現金化し、分配する
- 一方が住み続ける場合、他方が持ち分相当額を受け取る
- 住宅ローンが残っている場合の負担割合や処理方法
これらについて、具体的な合意が不可欠です。
年金分割と子どもに関する取り決め
熟年離婚では、将来の生活設計に直結する年金分割が特に重要です。特に専業主婦だった期間が長い場合、夫の厚生年金の一部を分割して自身の年金額を増やせる可能性があります。年金分割の手続きは離婚成立後2年以内(※民法改正により5年に延長予定)に行う必要があります。
また、未成年の子どもがいる場合は、以下の点についても合意が必要です。
- 親権者の指定
- 養育費の金額・支払い方法(毎月の金額、振込口座、支払期間など)
- 面会交流の頻度や方法
慰謝料の請求とその他の金銭的条件
配偶者に明らかな落ち度(例:不倫、DV、悪意の遺棄など)がある場合は、慰謝料の請求も検討できます。慰謝料の金額はケースにより異なりますが、数10万円〜数100万円程度で合意されることが多いです。
これらの金銭面の条件については、曖昧にせず、書面により明確にしておくことが後々のトラブル回避に繋がります。
【関連記事】
>離婚に伴う住宅ローンの整理
>離婚協議書に記載するオーバーローンはどのように記載する
>離婚協議書作成時のペアローンの適切な記載
離婚協議書の作成と公正証書化
取り決めた離婚の条件は、口約束で終わらせず必ず書面に残しましょう。夫婦間で合意した内容を文章にまとめたものを「離婚協議書」と言い、財産分与額や年金分割の方法、慰謝料の有無などを明記します。
書面化することで「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、後から約束が反故にされる事態を避けられます。さらに可能であれば、その離婚協議書を公証役場で「離婚給付契約公正証書」として作成することを強くおすすめします。
公正証書にしておけば、万一夫が金銭の支払いを怠った場合でも直ちに強制執行(給与や預金の差し押さえ等)を行える効力を持ちます。また、公正証書は公証人という法律の専門家が内容をチェックするため、法的に不備のない安心できる契約書となります。行政書士に依頼すれば、離婚協議書の作成から公正証書化のサポートまで受けられるため、不安な場合は専門家の力を借りて確実に手続きを進めましょう。
【関連記事】
>離婚協議書を公正証書にする流れは?
夫が熟年離婚を切り出す理由と男性心理
![]()
突然夫から離婚を求められると、「なぜ?」という疑問が頭から離れないものです。男性が熟年離婚を切り出す背景には様々な理由が考えられます。背景を知ることで、夫の言動を冷静に受け止め、対策を考える手がかりにすることもできるでしょう。
このトピックでは、夫側の心理や離婚を決意する代表的な理由について知り、今後の対応の参考にしていただきます。
老後への不安と人生観の変化
定年退職や子供の独立を機に、自分の残りの人生を見つめ直す男性は少なくありません。「このままの夫婦関係で老後を過ごせるのか」と不安を感じたり、第二の人生を自由に楽しみたいという思いから離婚を考えるケースがあります。
特に最近は「夫も熟年離婚を決断する時代」と言われ、妻だけでなく夫側にも長年の不満や孤独感を抱えている場合があるのです。老後の生活観の違いや価値観の相違が大きく、修復が難しいと夫が判断したとき、離婚を切り出すことがあります。
例えば、妻は穏やかな老後を望んでいても、夫は定年後に趣味や新たな挑戦に時間を使いたいと考えるなど、老後の生活の方向性が大きく異なる場合もあります。
他に好きな人の存在や自由への欲求
残念ながら、熟年離婚の理由として夫の不貞(浮気)や新たな異性の存在が背景にある場合もあります。長年連れ添った妻よりも新しいパートナーとの人生を選びたいという身勝手な理由で離婚を求めるケースです。
また、不貞ではなくても家庭という束縛から解放されたい、誰にも干渉されず自由に暮らしたいという欲求から離婚を望む男性もいます。いずれにせよ、こうした理由では妻に非がない場合も多く、突然離婚を切り出された妻にとっては理不尽に感じられるでしょう。
夫婦関係の積年の不満
実は男性は自分の不満や辛さを表に出さず我慢してしまう傾向があり、それが限界に達して突然離婚話を切り出すこともあります。男性側からの熟年離婚には、長年積もり積もった夫婦間の不満が爆発した結果というパターンもあります。
例えば、コミュニケーション不足によるすれ違いや、家庭内で自分の居場所がないと感じていた、あるいは些細な喧嘩の繰り返しで愛情が冷めてしまったなど、理由は様々です。
妻から見れば「突然」でも、夫の中では何年も前から不満が蓄積していた可能性もあります。男性は不満を言葉にしないまま抱え込むことも多いため、妻にとって寝耳に水の離婚話となってしまうことも少なくありません。「夫はそう考えていたのか」と理由を知ったからといって簡単に納得できるものではありませんが、理解の材料にはなるでしょう。
離婚が避けられないと感じたら妻がすべき準備
夫からの離婚の意思が固く、どうしても離婚を避けられない状況であれば、妻としては少しでも有利に、そして安心して新しい生活を始められるよう万全の準備をする必要があります。離婚はゴールではなく、その後に新たな生活が始まります。新生活を安心して迎えるためにも、事前の備えを怠らないようにしましょう。このトピックでは、離婚が現実味を帯びてきたときに妻が早急に取り組むべき準備について説明します。万全の準備を整えれば、離婚後の生活もきっと前向きにスタートできるでしょう。
経済面の見直しと財産の把握
離婚後の生活設計を具体的に考えましょう。まず、夫婦の財産状況をきちんと把握することが大切です。預貯金残高や持ち家の評価額、退職金の有無など、負債も含めて共有財産になりうるものをリストアップします。
その際、預貯金通帳の写しや不動産の権利証など財産の状況を示す資料も手元に確保しておくと安心です。離婚時にはそれらを適正に分与してもらう権利があります。また離婚後の収入源を確保するために、可能であれば就職やパート勤務など収入を得る手段も検討しましょう。
年金分割の手続きを忘れずに行うことも重要です。専業主婦であった期間が長い方は、年金分割によって離婚後に受け取る年金額が増えるため、将来の生活保障につながります。経済面の準備を周到に行い、離婚後に困窮しないための土台を作りましょう。
住む場所の確保
離婚後にどこに住むかは極めて重要な問題です。現在の自宅に引き続き住めるのか、あるいは新居を探す必要があるのかを早めに検討しましょう。夫名義の持ち家に住んでいた場合、離婚後は退去せざるを得ないこともあります。
その際には賃貸住宅を借りるか実家に戻るかなど選択肢を考えます。経済状況によっては公営住宅(市営住宅・県営住宅)への申し込みや、自治体の住宅支援制度、生活保護の住宅扶助なども利用できます。
ただし、収入や年齢の面で民間賃貸の契約審査が厳しくなる場合もあります。その際は保証会社の利用や自治体の住宅支援策を検討すると良いでしょう。せっかく離婚を決意したのに家が見つからず断念ということにならないように、住む家を確保してから離婚への第一歩を踏み出しましょう。
専門家のサポートを活用する
離婚に関する手続きや条件の取り決めには専門的な知識が必要です。離婚を目前に控えた段階では、ぜひ専門家の力を積極的に活用してください。例えば、離婚協議書の作成には行政書士のサポートを受けるのがおすすめです。
行政書士は法律に則った文書作成のプロであり、あなたに有利な内容を盛り込みつつ、公正証書にする際に必要な形式で漏れのない協議書を作成してくれます。また、調停や裁判を伴わない協議離婚であれば、弁護士に依頼するより費用を抑えながら専門的サポートを受けられる点も行政書士に依頼する大きなメリットです。
さらに、公証役場とのやり取りや手続きも行政書士が代行できるため、複雑な公正証書作成も安心して任せられます。行政書士と弁護士はそれぞれ専門分野が異なりますが、協力してもらうことで離婚手続きをスムーズかつ確実に進めることができます。プロのサポートを受けながら準備を進めれば、精神的な負担も軽減され、離婚後の新生活への不安も和らぐでしょう。
離婚の申し出は人生の大きな転機であり、不安と悲しみで押しつぶされそうになるかもしれません。しかし、離婚は同時に人生の再スタートでもあります。たとえ今は不安でも、適切な準備を整えることで新しい人生を自分らしく歩むチャンスにもなり得ます。決して悲観するばかりでなく前向きに新しい一歩を踏み出せるでしょう。大切なのは、自分の権利と将来をしっかり守ることです。一人で抱え込まず、専門家や周囲の力を借りながら、冷静かつ着実に対応していきましょう。
熟年離婚に伴う協議書や公正証書の作成はお任せください
![]()
当事務所は離婚案件を専門に取り扱っており、なかでも熟年離婚に関するご相談に重点的に対応しております。
ご依頼者様が本来の権利として受け取れる金銭を確実に受け取れるよう、最適かつ確実な方法で離婚手続きをサポートいたします。
サービスの特徴
きめ細やかな対応
ご依頼者様のご状況に合わせた、離婚協議書や公正証書を作成いたします。これまでに、ネット上のサンプルやテンプレートでは対応できないような難易度の高い離婚協議書や公正証書の作成も対応させていただいた実績があります。
柔軟な相談や業務の対応
対面、電話、オンラインなど、お客様のご都合に合わせた相談方法をご用意しております。さらに、当事務所では離婚協議書の作成に加え、公正証書の作成も取り扱っております。公正証書の作成については、全国的に対応しています。
明確な料金体系
事前にお客様のご状況をヒアリングした上で、サービス内容と料金の詳細をお伝えしますので、料金体系は明瞭にさせていただいております。
全国対応
当事務所は大阪市に事務所がありますが、離婚協議書や公正証書の作成については、大阪府、兵庫県、奈良県を中心に全国からご依頼を承っております。これまでに、東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご依頼を承ってまいりました。
離婚協議書作成の流れ
- 初回相談
まずは、電話や問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様の状況をヒアリングし、離婚協議書作成の記載内容などをお伺いし、御見積やご準備いただく書類等をお伝えいたします。 - 契約締結
上記1によってご依頼いただいた内容で契約締結をします。お支払は契約締結後5日以内とさせていただいております。 - 協議書の草案作成
離婚協議書、公正証書いずれのご依頼であっても、まずは協議書の草案をPDF等のファイルでご確認いただきます。お送りする協議書の草案をご夫婦でご確認ください。 - 協議書の修正等
作成した草案の内容について必要に応じて変更や修正をいたします。その際に、不明点や疑問点があればお気軽にお申し付けください。 - 協議書の製本と郵送
確定いただいた協議書を当事務所で製本し、郵送させていただきます。なお、公正証書とする場合には公証役場にて手続をいたします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| ⑴離婚協議書の作成と製本 | 44,000円 | 離婚協議書を作成し、製本までを対応させていただきます。 |
| ⑵離婚公正証書の作成サポート (上記⑴を含みます。) | 77,000円~ | 離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。代理調印が必要かなのかどうかで費用が異なります。 |
※)上記金額に実費がかかります。
当事務所にお任せいただくメリット
- 安心と安全をご提供します
法的知識と豊富な経験に基づいた、安全で信頼性の高い協議書を作成いたします。 - 時間の節約
煩雑な離婚協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことで、お客様の貴重な時間を節約できます。 - トラブル予防
将来起こり得るトラブルを第三者からの視点で予測し、それを防ぐための条項を検討させていただきます。 - 専門的アドバイス
離婚に関する法的な疑問や離婚後の手続なども専門家の立場からアドバイスいたします。
お問い合わせ
離婚協議書の作成について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に寄り添いながら、最適な離婚協議書や公正証書の作成をサポートいたします。
お客様の声
お客様からいただいたお声の一部はこちらをご確認ください。
![]()
【政府の記事】
日本年金機構「離婚時の年金分割」
法務省「年金分割」
法務省「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」
厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」



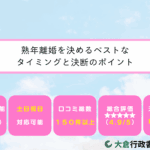
コメント